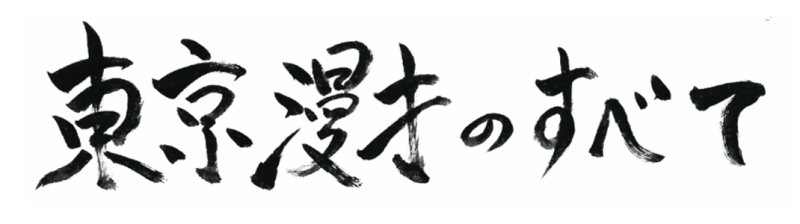町田たけし(二代目柳家三亀松)

柳家亀松時代
人 物
町田 たけし(二代目柳家三亀松)
・本 名 町田 武
・生没年 1922年2月22日~1998年8月19日
・出身地 東京
来 歴
町田たけしは戦後、落語協会の大看板として君臨した二代目柳家三亀松の前身である。長らく三味線と美声を生かした寄席の音曲師として活躍し、大名跡の柳家三亀松を継承したが、元々のスタートは漫才であった。
父は中国奇術の趙相元。ただし、養子という説もある。
叔父は九段下「洋菓子ゴンドラ」の創業者・細内源次郎、従兄弟には二代目社長・細内進がいる。業界紙『製菓製パン』などを見ると、「細内氏と亀松氏は親類に当たり……」とある。また、ゴンドラに出入りしている知人経由で伺ったところ、「(亀松の息子の)亀太郎さんとは縁戚に当たる」と細内オーナーが言っていた。
相元は町田秀子という徳島県の女性と結婚、日本に帰化同然の存在となっていた。そういった関係から母方の姓を名乗ることとなった。
親はたけしを芸人にする気はなかったものの、1927年に5歳で踊りの稽古に出、1929年に7歳で初舞台を踏む。
その辺りの事情は『東京かわら版』(1983年3月号)今月のインタビューに詳しい。
――師匠の初舞台というか初高座はいくつのころなんですか?
●学校一年の時分だから、六つのときですか。場所は浅草の江戸大盛館。その当時ここは演芸会のメッカですよ。いまの雷門助六さんが五郎で出ていたり、先代の(神田)ろ山、うちの師匠もかけ出しで出ていました。
親父が奇術師で、その前にちょこちょこと踊ったりしました。芸ごとは踊りが最初で、それからバイオリン、三味線と習っていたんです。バイオリンをやめた理由は、師匠に「亀松(現・三亀松)、お前バイオリンにするのか三味線にするのか?」ときかれた。三亀松の弟子なのにバイオリンにしたら、私しゃ石田一松の弟子に鞍替えしなきゃならない。それで三味線の方を取った。初めのころは着物がなくて、洋服着て高座に上がったけれど、おかしな格好だったでしょうねェ。
落語協会に籍を置いたのは昭和11年。三亀松に正式に弟子入したのが29年で、5月に亀松の名前をもらって、高座に戻ったわけなんです。黒門町(故桂文楽)の一門に入れてもらった。その時、黒門町の身内になったんだから、失敗のないようにしようと思いましたね。
初舞台間もなくして、父から「三亀松の弟子になるか」と問われたことがあった。たけしは「なりたい」と答えたものの話は保留になった。
当人はその時の謎を回顧して、「同じ釜のメシを食った同士が片方は偉くなったけど、片方は落ちぶれちゃった。親父としても頼みにくかったんじゃないですか」と推測している。
『國際映画新聞』(1939年7月号)に掲載されたアトラクション芸人の名鑑の中にその頃の芸を記したものが出ている。
趙相元・町田たけし 曲藝。趙相元の奇想天外な奇術と、その息町田たけし少年の三絃バイオリン曲弾、舞踊等は観る者の眼を瞠さずには置かぬ至藝の極。派手な短時間ショウとして推薦。
また、10歳くらいになると父の仕事に付き添う形で関西へ移住し、大阪や京都を転々とした。幼い頃は奇術や楽器の他に踊りも得意としていたそうで、京都では両面踊り(お面を顔面と後ろにつけてあたかも一人二役で踊るようなネタ)を覚え、幼い頃はこの芸が看板であったという。
しばらくの間は父の後見として高座に出ていたが、満州事変以降は父に「敵国の芸人」というレッテルが貼られた上に、父は糖尿病にかかってしまった。
家庭の事情や芸の事情もあり、漫才師へ転身。
東京吉本へ入り、妹と別れたばかりの耕田実とコンビを組み、「耕田実・町田武」を結成した。
達者な少年漫才として売り出し、東京吉本で一枚看板を張っていたこともあった。当時の花月系列や浅草の漫才席に出るなど人気はあった。
遺族の話では「しゃべくり漫才と楽器なんかを生かした漫才だった」らしいが、今となっては謎が残る。
一方、戦時中は長らく「敵国人」と白眼視されたそうで、『東京新聞夕刊』(1964年6月4日号)掲載の「人情寄席ばやし」の中に――
浮き世節(三味線漫談)の柳家亀松は、中華料理を食っていると「あのとき芸を捨てて中国籍のままで通したら、今ごろはナントカ飯店ぐらい経営して、実業家でいられたかも知れねえな」と思うことがある。
亀松は戦前、三代目小さんのヒザガワリぐらいを勤めた中国人奇術師・趙相元(ちょうそうげん)のむすこである。母親はむろん日本人なんだが、中国籍で育った。大正十一年、浅草芝崎町の生まれ。父の趙さんは大正七年に来日して寄席などに出演、楽屋で何か話しかけられると「ヘエ、アタシ二十四歳ヨ」で通したという逸話が残っている。趙さんは、亀松が十八のときなくなった。
四歳ぐらいから、父親にくっついて舞台に出た。巡業などの関係で小学校は三年でストップ。そのかわり三味線、踊りなど日本の芸を修業、柳家三亀松に私淑してその門にはいり、今ではオヤジといえば三亀松のことである。まわりは日本の芸人だし、浅草の生まれだし、自分は根っからの日本人のつもりだったが、中国籍なばっかりにいろいろと苦労した。
戦前は銀座から東、築地方面へは立ち入り禁止だったし、横浜・伊勢佐木町の花月劇場へ行くのに、何時何分に家を出て、どこの停留所で市電に乗って、東京駅へ何時何分着、何時何分発の電車で横浜へ行って、どの道を通って楽屋入り――と詳細な届けを警察に出さねばならなかった。好きな女ができて結婚したいと思っても、中国籍とわかると、こわれた。
だから芸の次に、彼の頭の中を占めていたのは、いかにして日本籍になるかということだった。戦争が終わる。三国人の天下がきた。それでも修業に夢中になっている彼に、仲間の芸人のあるものは「バカだね君は――そのままでいりゃ金もうけのしほうだいじゃないか」と教えてくれたが「オレの気持ちはわからない」とかなしかった。
あらゆる手ずるを求めて奔走して、とうとう昭和二十六年に晴れて日本人・町田武になれた。いいことは続くもので、当時、左の眼球をヒョンなことから痛めて、治療に行っていた日赤椎名町診療所の看護婦さんと愛が芽ばえ、結婚した。現夫人の純江さんである。
「すぐ腹が立ってポンポンけんかしちまうし、可と思うとバカに引っ込み思案になったりして典型的な江戸っ子だと思ってるわけですが、ことに修業についちゃあネバリ強かった。やっぱり中国人の血もちっとは流れてるんですね」
昭和三十六年五月、亀松は亡き父の二十三回忌法要を盛大に営んだ。豊島区椎名町の家には、趙さんと三亀松、二人のオヤジの写真が掲げられている。
とある。
1939年12月、父が亡くなった後は母を抱えて一人で家庭を支えることとなった。
1943年半ば、出征に伴い、耕田実とのコンビを解消。数年間戦地勤務となる。耕田は後に妹とコンビを組んだ。
終戦後は無事に復員し、高座へ復帰。元相方の実が腹話術に転身していたこともあり、音曲漫談として一本立ちすることとなった。
当時はバイオリンや三味線を弾きながらノンキ節や流行歌の替歌を唄う不思議な芸を演じていた。「三味線の石田一松」という異名もあったという。
1951年、日本国籍を取得。正式に「町田武」が本名となった。
この頃、眼病を患った際に出入りしていた病院に勤務していた女性と結婚している。
1954年、桂文楽門下へ復帰し、落語協会に入会。文楽の斡旋で、念願かなって柳家三亀松の門下へ正式に参じる。
同年5月に「三代目柳家亀松」を襲名。正式な寄席デビューは1954年10月、麻布十番俱楽部上席だろうか。
襲名以降、三亀松同様に「三味線粋曲」を称するようになり、これまでのバイオリンと洋装姿を捨てて、三味線と邦楽で勝負するスタイルに転身した。
初代とは打って変わって「三道楽をほとんどしない真面目人間」であったものの、三味線や踊りの腕前は初代よりもよく、『とっとりとん』『大津絵』『都々逸』などの寄席の音曲から『たぬき』『櫓太鼓』などの難曲を弾きこなした。
また、踊りも達者で若い頃は音曲を演じた後にハチマキなどをして踊ることも珍しくなかった。
堅実で卑しさのない芸風は寄席や放送などに向いていた。
桂文楽や三遊亭圓生をはじめ、多くの落語家に可愛がられ、彼らのヒザ前などに出ることも珍しくはなかった。
芸にうるさい圓生にも気に入られ、圓生一行や圓生独演会の色物として全国を回ったこともある。
さらに豪快な三味線の腕前を見込まれる形で林家彦六の芝居噺に参加し、芝居噺の中で出てくる大薩摩を演奏するようになった。
音曲の素養のあった橘家圓太郎と組んで、唄を圓太郎、三味線を三亀松が担当し、芝居噺を盛り上げることもあった。一部の映像は今も記録映像として残っている。
また、戦後の隠し芸やお座敷ブームでは、日本俗曲学院なる学院と手を組んで「かくし芸教室」「都々逸教室」などのレコードを発売している。
1964年10月30日初日の日劇ミュージックホール公演『やむにやまれぬ夜』に特別出演。
三亀松亡き後も、三亀松の芸を受け継ぐ貴重な逸材として寄席を中心に活躍。音曲大不況の時代に、寄席の音曲を守り続けた。
1977年には長男・時久が入門。「柳家亀太郎」と名乗る。次男も音曲の道に入ったが、間もなく廃業している。
亀太郎入門後は「亀松・亀太郎」のコンビで出るようになる。古風な音曲を得意とし、まず音曲や俗曲をたっぷり聞かせてから、弟子の亀太郎を呼んで合奏をしたり、一つの三味線で二人で演奏する曲弾きなどでお客を魅了した。
1980年3月31日、新宿末広亭において「二代目柳家三亀松」を襲名。色物では珍しく襲名披露を華々しく行っている。
その後は三亀松の名を汚さぬように奮闘をつづけ、平成初頭まで三味線粋曲の第一人者として君臨した。晩年は三遊亭金馬や月の家圓鏡(八代目圓蔵)の独演会のゲストに出たり、若手落語会で指導役に回ったりと落語協会の大幹部としてもふるまった。
1997年12月8日、新宿末広亭夜席の高座を終えた直後に楽屋で脳溢血を発病。すぐさま病院に運ばれ、一命は取り留めるもその後は昏睡状態であった。
1998年8月19日、脳溢血後遺症呼吸不全のために死去。
死後まもなく発行された『ぞろぞろ41号』に追悼記事と柳家亀太郎の談話が出ている。
鮮やかな三味線の曲弾きと、粋な都々逸、さのさ、新内などを聴かせてくれた二代目・柳家三亀松師匠が、亡くなった。昨年12月に倒れてからの療養の甲斐もなく、本年8月に6歳で永眠された。正楽師と同様に、実子が同じ世界に居て、寄席の高座で活躍している。昭和52年に父である三亀松師に入門して、昭和63年にひとり高座を務めるようになるまで約10年間、父と一緒に高座で三味線を弾いた柳家亀太郎さんが、その人。子として、弟子として、想い出を語っていただこう。
――師匠から離れてひとり高座になって、もう随分になりますが、当初はどんなお気持ちでしたか。
「噺家の場合は、前座の頃から一人で高座に上がりますけど、私は約10年間、いつも親父と一緒でしたから、緊張しましたね。今までのようにお客様に受けなくちゃいけないのに、受けない……。弱っちゃいましたね(笑)。親父の偉大さが身に滲みました」
――お宅での三亀松師匠は、どんな方だったのでしょうか。
「どちらかというと恐い人だったですね。親子だから仕方がないんですが、 子供としてのしくじりが、弟子としてのしくじりにもなる訳だし……」
――われ〳〵楽屋仲間にとっては、三亀松師匠といえば、例の「おわァん」 という独特の挨拶が忘れられないのですが。
「あれは「ご苦労さん」という言葉が短くなって「おわァん」になって(笑)。アニ以前、浅草演芸ホールの楽屋に入ってきた(古今亭)菊丸兄さんが、先代の志ん馬師匠に「おわァん」て挨拶して、大しくじり(笑)。先輩に向って、 なんだその挨拶は!って小言になっちゃって。その後、私が菊丸兄さんから叱られました。お前の親父さんのお陰で志ん馬師匠をしくじったって (笑)」
――お客様にはお気付きでない方が多かったと思いますが、師匠は髪を付けてらっしゃったんですよね。
「池袋演芸場が新装される前のことですが、雨の降っている日で、傘をさしたまま転んでしまったそうです。まわりに人がいて恥しいので慌てて立ち上がって、演芸場の楽屋に入る。いつもは見ないのに、楽屋の鏡を見たら、無いんですって、頭の上に(笑)。楽屋のみんなは畳に座ってるから、まだ立ったままの親父の頭の上には気付かない。
すぐに、さっき転んだ場所まで戻ってみると道に落ちてました、誰にも拾われずに(笑)。慌てて頭に付けたら、雨の雫がダラ〳〵って」
――いずれは師匠のお名前を襲名されることを考えていらっしゃいますか。
「こればっかりは自分一人で決められることじゃありませんからね。少しでも親父の芸に近づけるよう精進して、 まわりの方々から認めていただけるよう頑張ります」
弟子として、師匠の名前を継げるようになることが、亡くなった師匠への何よりの供養になることでしょう。
亀太郎さん、応援していますヨ!