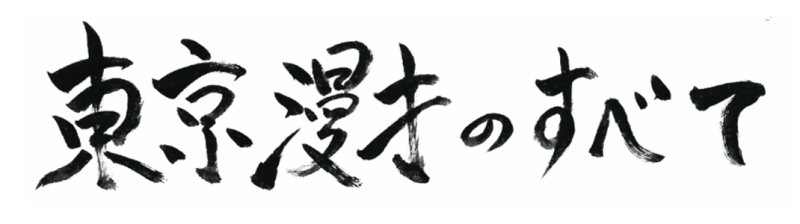サンサンズ

宮崎じゅん(バンジョー)・とまりれん(ギター)・ハウゼ畦元(アコーデオン)
人 物
人 物
ハウゼ 畦元
・本 名 畦元 直彦
・生没年 1932年1月1日~2025年6月22日
・出身地 満州 旅順
とまり れん
・本 名 藤本 貢
・生没年 1951年4月29日~ご健在
・出身地 広島県 尾道市 百島
宮崎 じゅん
・本 名 宮崎 純
・生没年 1932年5月12日~没
・出身地 ??
来 歴
サンサンズは昭和40年代から50年代にかけて活躍した歌謡漫談グループ。元漫才師でアコーデオン奏者のハウゼ畦元、演歌『氷雨』を作詞したとまりれん、後にホラッチョ宮崎と称した宮崎純の三人で結成された。
ハウゼ畦元の経歴は「第一球」のところで詳しく記した。 立教大学在学中に芸人となり、声優、役者を経て、大空平路・橘凡路の紹介で漫才師に転身。相方を失ったばかりの春日三球とコンビを組んで「第一球・三球」。後に大空平路とコンビを組み「大空平路・凡路」。 平路が芸能界を辞めたのを機に漫才界を離れ、歌謡漫談に転身した。根がアコーデオン奏者だけあってか、歌謡漫談界とは仲が良かったという。
1971年頃にボーイズとして活動するようになり始め、メンバーをとっかえひっかえしながら「とまり・宮崎・ハウゼ」の三人体制となったという。なお、ハウゼ氏当人からは「歌謡漫談に移った当時は大空凡路の名前でやっていましたよ」と伺っている。
ギターのとまりれんは尾道百島という島っ子として生まれ育った。
『日本の作曲家 近現代音楽人名事典』によると――「高校卒業後、上京して室内装飾の会社に入るが2年足らずで退職し、バンドマンのボーイや歌手見習となる。1972年にサンサンズに加入」との由である。メンバーでは最年少であった。
宮崎じゅんは元々「スリートーンズ」という歌謡漫談チームに所属をしていた。スリートーンズは相当人気があったため、キャリア的には一番上であった。
元々は日本大学芸術学部出身の演劇家で、八波むと志に師事したというコメディアンであった。『歌謡漫談読本』によると――
顔中の栄養の全部を吸いとった偉大(?)なマユ毛のミヤちゃん(宮崎純)は、日大芸術学部出身。東宝ミュージカルから、テレビ等に出演して六年、 その後三十六年にボーイズを志し、大型から小型ミュージカル(?)に転向した。故八波むと志の愛弟子です。
1961年に若菜春夫・高橋わたるとともに「スリートーンズ」を結成。コーラスを生かした明るい歌謡漫談とベル鈴と称した珍楽器で人気を集めた。
1960年代の人気はなかなかすごく、東宝名人会に出演したり、テレビに出ていたりする。後年「売れない芸人」と揶揄された宮崎であるが、それは嘘である。
1970年代に入り、宮崎はスリートーンズを脱退。ハウゼも漫才を辞め、とまりれんを入れ込む形でトリオを結成。ボーイズ協会に所属をして演芸場や寄席に出るようになった。
ハウゼ氏によると「何か計画をしてグループを組んだ」というわけではなく、事務所や関係者のすすめでトリオを組み、それで活動していたという。
ハウゼはアコーデオン、宮崎はバンジョー、とまりはギターを担当し、オーソドックスな歌謡漫談を得意とした。テーマソングをハウゼ氏から伺おうとしたが「老齢のせいで忘れてしまった」。とまりれん氏なら知っているかもしれない。
一方、1970年代半ばに入るとハウゼがアコーデオン奏者に転身して、故郷の鹿児島へ行ってしまった事やとまりれんが作詞家になったこともあり、チームは事実上の解散となった。
ハウゼ氏が鹿児島へ行った理由は伺ったことがある。
「家庭的な理由とか芸能界への疲れとか、そういうのもありましたし、なんせ鹿児島は暑い所ですから4月から10月までビアガーデンやっていたんです。当時はカラオケがまだ普及しておりませんからね、アコーデオンとエレクトーンを弾けたのでそういう場所に出入りしておりましたら、高級ビアガーデンから『ギャラはいくらでも出すからウチに来ないか』と誘われるようになったんです。鹿児島は戸籍上の実家でございますし、悪いところではない。当時、変な高座に出るよりそちらの方がギャラも待遇もよかったので、結局鹿児島へ移住して十年近くおりました」
一方のとまりれんはコツコツと出演料を貯めて、西麻布に「スナック・ぷすはうす」を開業。夜はバーマンとして働くようになった。そのかたわらで作詞の勉強を始めたという。
1977年2月のある寒い夜、スナックにやって来た女をモデルに『氷雨』を書きあげ、駆け出しの歌手であった佳山明生に提供した。『熟年ばんざい スペシャルインタビュー 佳山 明生さん』によると――
デビュー曲『氷雨』は、人々の心に浸透し、昭和の名曲として燦然と輝いている。作詞・作曲は、当時はまだ無名だった彼の友人、とまりれん氏。実際にあった一夜の出来事からこの歌詞が生まれたという。
「音楽創作の傍らスナックを営んでいた彼の店で、凛とした着物姿の女性が一人お酒を呑んでいて…。彼女がカウンター越しに話した言葉を、そっとコースター30枚に書きしたためたと言います。それを繋げて曲にしたのが『氷雨』。彼女のセリフが、そのまま歌詞になったのです。
1977年12月、日本コロムビアより丸山の歌唱で発売された。当初は売れなかったものの、丸山の必死の宣伝や地方巡業などで徐々に売れ行きを伸ばしていった。
1983年、日野美歌がカバーした『氷雨』はヒットを飛ばし、この年の紅白歌合戦で披露されている。また、丸山版もこの年の「第25回日本レコード大賞」のロングセラー賞を獲得している。
これに伴い、とまりは完全に芸人を辞め、作詞家として生きることとなった。今日は東京の事務所や邸宅を整理し、故郷の百島で静かに暮らしていると聞く。
一人残った宮崎じゅんが新人を引き入れ、「サンサンズ」を受け継いで高座に出たが、長くは続かず1978年に正式に解散。
解散後、宮崎じゅんは「ホラッチョ宮崎」と改名し、トランペットやバンジョーをいくつも持って現れ、それをドンドンジャンジャンと曲弾きする音楽漫談へと転じた。
かつての人気と比べるといささか寂しいものであり、音楽芸人としては売れなかったが、その不思議な芸名と人柄が評価され、ビートたけしの『オールナイトニッポン』でたびたびネタにされた。たけし経由で名前を憶えている人もいるだろう。
かつての相方である若菜春夫氏によると「宮崎さんは既に亡くなっている」との由である。
歌謡漫談を去ったハウゼ畦元は、鹿児島で長らく音楽家として活躍。平成初頭に家族や親族の残した鹿児島の財産を整理して、再上京を果たした。後年、深谷にいい土地があるのを知り、これを購入。最期までここに住んでいた。
平成以降はアコーデオン漫談家、ボーイズ協会会長の坊屋三郎のバックバンドとして活躍。そのかたわらで深谷で「手風琴」というカラオケ喫茶兼カラオケ教室を開き、講師として活動していた。
70代まで東洋館などの高座に出ていたというが、坊屋三郎が亡くなったことや当人の老齢もあり、それ以降は深谷の手風琴でカラオケ教室を開催する日々を送っていた。
当方は2019年に何度か氏の下を訪れ、昔の話を伺ったことがある。それも遠い昔の話である。