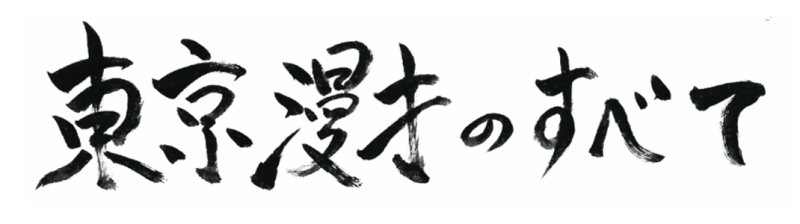二代目鏡味小仙(太神楽)

鏡味小仙

ハワイ巡業の広告
人 物
鏡味 小仙(二代目)
・本 名 生駒 弥太郎
・生没年 1918年5月7日~1981年12月5日
・出身地 大阪
来 歴
二代目鏡味小仙は戦前戦後、太神楽を支えた一人。鏡味仙翁の養父であり師匠。落語協会の人気神楽師であった仙之助・仙三郎たちの師匠でも知られる。今日の落語協会系丸一と仙翁丸一の人々はここから出ている。
出身は大阪、父は上方落語家の桂鯛蔵。
鯛蔵は当時盛んであった寄席の東西交流で上京することとなり、小仙も同行。父はそのまま東京に定住し、関東大震災後も東京に住み続けた。
父が旅回りが多く家を不在にしがちであること、鯛蔵と鏡味小仙が親しかったこともあり、鯛蔵は小仙に頼んで、息子を預かってもらうようになった。当人は『日本の芸談 第7巻』の中で以下のように語っている。
御存知の方もあるでしょうが、林家正蔵さんの友だちで、亡くなった今輔さんらと革新派を作ったりした上方落語の桂鯛蔵――これが私の実の父親なのです。
昔の咄家さんにはいろいろ面白い人も多かったが、私の親父も奇人に数えられる一人ではないかと思うのです。とにかく大変な人でした。どうしようもない道楽者で、女房を変えること四度、私のおふくろは二人目で、次に神戸へいって三人目と一緒になり、それから岡山で四人目と住み、 最後には満州にまでいき、お坊さんになってしまった。今様にいえば、翔んでいるというのでしょうか、まるで糸の切れた凧みたいに、あちらこちらと放浪して歩いた人でした。
幼少のころの親父との思い出は、東京へ連れられてきて、浅草で住んだ何か月だけしかありません。先代も親父とは友だちだったもので、「あちこち飛んで歩いてちゃことだろうが。どうだい、お前の仲を俺ンとこにくれないかい」と親父に交渉し、私は預けられた恰好で丸一に入り、そのままになってしまったのでした。
私が親父に再会したのは、十八歳の時です……。もはや仏門に帰依した後で、「どうだい、俺の跡をとって坊主にならねェかい」といいましたが、いやはや、熱中して拝んでいる親父の姿を見ていると、「ああ、とても僕にはこんなことはできないや」そう思ったものでした。
1925年、初代鏡味小仙の弟子となる。
早くから厳しい稽古を仕込まれ、曲芸や獅子舞を会得。「鏡味仙寿郎」と名付けられる。間もなく小仙社中の一員となり、師匠と共に寄席や劇場を回った。
学校では居眠りばかりであったというが、先生はお目こぼしをしてくれたという。一方、手先が器用で絵や工作ではいい成績を取るため、先生から「大工や職人にならないか」と言われるほどだった――と『日本の芸談 第7巻』の中で語っている。
1931年末ころに「丸一子供連」として独立。『映画と演芸』(1932年8月号)の寄席欄に「太神樂の小仙の弟子の仙壽郎(右)と福三郞兩君」という若かりし頃の姿が紹介されている。
戦時中まで第一線で活躍していたが、1945年初頭に出征。帝都座出演中に赤紙が届いたという。
福岡小倉の小倉十四連隊に配属となり、「本土決戦部隊」として訓練を受けた。三十近い初年兵として散々上等兵に虐められたというが、曲芸ができる所から慰問団に回されるようになる。当人は『日本の芸談 第7巻』の中で
そうこうしているうちに、なぜわかったのだろうか、私が曲芸ができることが知れてしまったのです。それまで、 曲芸のことはかくしていて、入隊当初、古参兵から一人一人、「お前はシャバでなにをしていたか」と訊かれたとき、「私は、なにもしていませんでした」と答えたのでした。 なにしろ、以前に中国各地から満州、蒙古まで慰問に廻っていたころは尉官待遇で、ちゃんと当番兵はつく、移動には一個小隊が護衛する、という有様だったのが、赤紙一枚で引っぱり出されればただの一兵卒。莫迦莫迦しいという気持もあって、空ッとぼけていたのです。
それがバレてしまった。と、それからというもの、お座敷がかかるわかかるわ……。だけど、はじめ将校さんに呼び出されて命令されたとき、
「曲芸をやれったって、道具がなけりゃできません」
と、答えた。道具はなんとか用意しよう、どんなものが入用なのだ、というから、
「せめて揆と唐傘くらいは……。湯呑や土瓶はなんとかなるから」
そこで、日ごろ横暴だった上等兵あたりがノコギリをひいて、せっせと揆作りです。
部隊同士で、演芸大会とかなんとかで競い合うものだから、芸のできる者は結構重宝がられたものです。どこそこへいってこい、といわれると、道具を担いでいく。演芸会場へいくと、まず、「空ッ腹じゃ曲芸はできない……」なんて、担当の者にいう。すると、飯をたらふく食べさせてくれる。一度などは、あまりガツガツ食べすぎて苦しくなり、曲芸ができなくなったこともありました。
いろんな芸のうちでも、特に曲芸はうけましたね。
ところが、部隊へ戻ってみると、私の分の仕事がそのまま残っているのです。みんな分担してやっているので、他人の仕事までやってくれる者は誰一人いないのですよ。しかたがない、仕事はやりました。が、業腹なので、曲芸の撥などの道具は燃やしてしまったのでした。
また、お座敷がかかる。私は平然と、
「道具がありませんッ」
どうしたのだ、と不審気に訊くので、「曲芸をやるのはいいが、戻ってから仕事をさせられるのではたまりません」
それ以来、曲芸専任になりました。そのうちに終戦を迎えたのですが、八月十五日だということは知りませんでした。部隊にラジオはないし、麓の村々にも一台もない。知りようがなかった。だけど、連隊の上の連中がトラックで軍需物資をはこんで逃げてしまった後に、なんとなく終戦になったんだと感じたもので、はっきり日本が敗けたのだとわかったのは九月に入ってからでした。だけど、上の連中がいなくなってしまったので、下士官クラスでは解隊復員の手続きがスムーズにいかずもたもたの連続。軍規はゆるんで野放図に、だらしなくなって、私などは食い意地のほうだから、軍の物質を遠慮なく食べまくったものでした。私共兵隊にさんざっぱら饑じい思いをさせときながら、物質は結構豊富に残されていたのです。
1945年11月の除隊後は父と妻がいる岡山(吉備郡弥高にいた模様)を目指して帰還。父と妻と再会することができた。
一方、慰問のおかげで食事には不自由せず、帰って来た時はずいぶんと太っていて、夫人から「どなた?」と言われるほどの始末であった。
当時、鯛蔵は日蓮宗系の僧侶と祈祷師をやっており、山寺の管理人をやっていた。小仙夫婦もその手伝いを始めたが、寺の生活は凄まじく原始的であり、水や電気もろくにない状態であったそうで、『日本の芸談 第7巻』の中でも――
軍隊もひどいところでしたが、親父の寺もひどかった。
電気もなければ、水もない、まるで仙人の暮しのような環境でした。水汲みは山を下りなけれならない。これが大変でした。だから、雨でも降ろうものなら、家人総出で器を外にいっぱい置き、貯った雨水を大事に大事に用いたもので、一つの水を幾通りにも使うのが当たり前の事でした。 灯りにしたって、電気がないのですから、暗くなれば寝る
しかない。そんな生活を一年間しましたか。 さすがにうんざりしたものです。
だが、親父は結構泰平楽で、そんな暮しを屁とも思っていない顔付きでした。「とても、ついちゃいけないよ」
それでも私だって、お経の真似事ぐらいはやりました。 親父の宗派は、日蓮宗系の一種の密教でしたから、祈禱をしたり、狐憑きをおとしたり、ひどいのになると他の祈禱師と、まるで直木三十五の『南国太平記』にあるような呪組合戦をやった事もありました。そんな経読み三味の中で思ったことは、
「死霊はおとせるけど、生霊は怖い」
という事でした。ま、お布施や喜捨で暮しをたてる坊さん稼業は、水商売や芸人と同じようなものですね。
一方、1946年正月、寄席中継に出たという記録があるため、「復員→一度東京へ帰還→岡山へ疎開」の流れだろうか。
1946年秋、上京し芸能界に復帰。同年10月にはすでに東京の寄席へ出ている様子が確認できる。
東京堀切に所有していた家作に居を構え、再び寄席や劇場へ出勤するようになった。
この頃、田舎から戻って来たたぬき家金朝とコンビを組み、「丸一仙寿郎・金朝」として落語協会に復帰。古い仲間を集めて進駐軍慰問などにも参加をした。
華々しい太神楽の技は進駐軍慰問の花形となり、しばらくの間は進駐軍慰問で稼いでいた。
1947年5月、師匠の鏡味小仙が死去。最期までよく面倒を見たという。亡くなった後は兄弟子の丸一時次郎と共に丸一を支える大黒柱となった。
1949年7月、娘の美恵子が誕生。幼い頃から曲芸と曲独楽(赤井如水から習う)を仕込まれ、「鏡味弥生」として自身も高座に出た。
1949年11月、鏡味家から「一代限り」という約束で二代目鏡味小仙を襲名。襲名披露は上野鈴本、人形町末廣で行われ、色物襲名としては異例のトリを取っている(ただし表看板は落語が主任だった模様)。この時、相方の金朝も「小金」を襲名している。
襲名と前後して義姉(妻の姉)の次男坊を養子に迎え、「鏡味仙寿郎」を名乗らせて後継者とした。
1951年春、奇術の松旭斎天菊、チャンバラの大河内俊雄と三枚看板でハワイ巡業。鏡味次郎、鏡味小松、鏡味小金も同行した。
小仙の聞書きでは「仙寿郎も連れて行きたかった」というが年齢や諸事情で連れていけなかったという。
『ハワイ報知』(1951年4月10日号)の番組紹介によると以下のような芸を演じたという――
ホノルル消防署員は例年通り、署員家族、遺族などの救済資金募集カーニバルを催す。来る十三日から二十一日晩まで毎晩六時十五分と八時半の二回シヴィック公会館で賑々しく行ふ。本日の別項広告の通りである。各国人向きのプログラムを組み、有名人一行がアメリカ本土からも来る事になつており、日本からは去る六日の便船で太神楽曲藝十三代家元鏡味小仙一行四名と△松旭齋天菊一行四名とが來布してをる。
松尾兄弟興行部の招聴した一行八名である。「外国に出しても恥しくない」折紙つきの藝人であつて経歴は去る六日の布哇報知に發表された通りである。演目は次の通り
天菊一座演目
▲奇術の部
一、飛行カード
二、ジョーゴに水
三、布の色變り
四、魔法の箱
五、指抜き
六、玉子のカップ
七、袋拔け=大きな袋に少女一人を入れ、客席から一名登場して袋の口を縛り、更に見物によく調べてもらひ、太夫の掛声と共に外に居る太夫と袋の中の少女とが一瞬に入れ替る奇術
八、その他数種
▲水藝の部
一、剣の水
二、水を満たしたカップより水精噴出
三、羽子板の水
四、あやめの水、花の水
五、太夫並に登場全員より水の噴出
六、剣、羽千枝、ボンボリ、あやめ(花)、其他舞台裝置から水の噴出
七、舞台全部から噴水
小仙一座演目
一、タイマツ(火焰撥)
二、ナイフ(剣の曲)
三、傘の曲(末廣狩)
四、水の曲
五、皿の曲
六、土瓶の曲
七、一つまりの曲
八、五階の曲
九、かごの曲
十、撥の曲
十一、獅子舞
十二、源三位頼政
十三、二人羽織
十四、象の曲
十五、塩原多助(馬)
十六、川中島(馬)
以来、落語協会を軸に寄席や劇場で活躍。二代目丸一小金とは名コンビと称され、近代化する太神楽界の中で数少ない「太夫と道化」の型を守るものであった。
おっとりとした風貌と芸風、江戸前で確かな曲芸の腕前は高く評価され、寄席定席のみならず、名人会やテレビなどでも取り上げられるほどであった。
1953年頃、病気に倒れた二代目翁家和楽の跡を受けて、二代目太神楽曲芸協会会長に就任。「太神楽の古い芸や茶番を守るべき」という理念を掲げた。
当時生き残っていた古老たちから茶番やお囃子、曲芸などの作法や手順を聞き、これを採録。若手たちに稽古をつけた。
さらに有識者やお旦那衆の協力を経て、深川不動への太神楽奉納、街回りの復活を成功させた他、本田安次、永井啓夫、宮尾與男、中村茂子などの学者たちとも交流し、太神楽の知識や経験を伝えた。
1955年、知人の息子である山原澄(鏡味仙之助)が入門。少し遅れて山原の友人・大木盛夫(鏡味仙三郎)も入門。
小仙は仙寿郎と仙之助・仙三郎の3人を息子同然に可愛がり、厳しく芸を仕込んだ。
1962年秋、レコード集『江戸の神楽と祭囃子』が評価され、芸術祭賞レコード部門奨励賞を受賞。
初春の寄席の高座に「寿獅子」の企画を通し、毎年丸一一門が寿獅子を踊るようになったのもこの小仙の功績によるところが大きい。
1971年12月4、5日、国立劇場において「万作芝居と茶番狂言」を開催。茶番を復活させた。
1973年秋、体調不良から心筋梗塞を起こし、入院。これ以降、心臓病に苦しむようになった。
自らの衰えを悟った小仙は、1974年、会長職を柳家小志んに禅譲。名誉会長に就任した。
以降は曲芸や獅子舞は若手に任せて、口上や後見で高座に立った。
1978年10月21日、木馬亭で開催した太神楽曲芸協会の公演「太神楽~その芸の魅力~」が評価され、1978年度芸術祭優秀賞受賞。1979年2月には「東京都無形民俗文化財」に指定される。
1979年春頃まで高座に出ていたが、間もなく寄席の高座は退いた。その後は入退院を繰り返していたという。
1980年5月、江戸太神楽保存会より研究書『江戸太神楽』を発行。
1981年1月9、10日、国立劇場「万歳と松囃子」で獅子舞の太鼓を勤めたのが最後の高座だった模様。
1981年12月5日、心不全のため、足立区西新井病院で死去。63歳没。