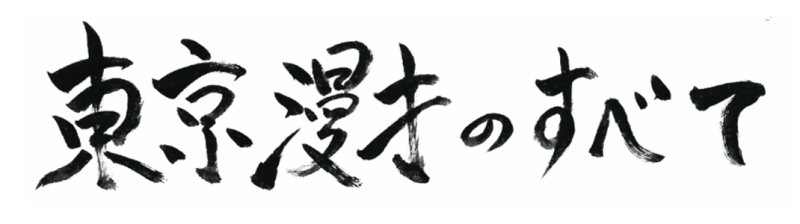ザ・ローカル(ローカル岡・三田宗司)

ローカル岡・三田宗司(右)
人 物
人 物
ローカル 岡
・本 名 岡田 満
・生没年 1943年12月13日~2006年1月16日
・出身地 茨城県 那珂市
三田 宗司
・本 名 三田 惣次
・生没年 1943年12月10日~没?
・出身地 群馬県 邑楽郡
来 歴
ローカル岡の前歴
漫談家「ローカル岡」が漫談家として独立する前に組んでいたコンビ。落語芸術協会に所属し、寄席の色物漫才師として出演を続けていた。古風な音曲漫才を得意とした。
出身は茨城県那珂市。幼い頃から茨城弁の中で育ってきたせいか、生涯茨城弁が抜ける事はなかった。
高校卒業後、職業訓練校を経て溶接工をしていたが芸人の夢をあきらめきれずに、工場を辞めて上京。
1965年、新山悦朗・艶子の門下に入り、「新山セイノー」と名乗る。
弟弟子(後の新山えつや)と共に、新山サイノ―・セイノーを結成し、木馬館でデビューをした。
この頃は不器用な芸人だったそうで、新山ノリロー氏曰く――
「サイノーは達者だけど、セイノーはハッキリ言えば、訛りもきついし喋りも達者じゃなかったから、本当に不器用って感じがした。あれだけ売れるとは思いませんでしたよ」。
若手として木馬館や松竹演芸場の前座として活動したが、3年ほどでコンビ解消。コンビ解消後は「新山セイノー」名義で漫談や司会で細々と活動を続けていた。
1978年、引退した岡三郎の後釜として、シャンバローに参加。柳四郎が連れて来たそうである。
柳四郎のご遺族曰く「そこそこ楽器も弾けるし、物も書けるし、お笑いもやっている、そういう才能を見込んで連れて来たのだと思います」。
メンバー入りに際し、「二代目岡三郎」を襲名。ギターを抱えて高座に上がり、ボケ役に徹していた(その頃、柳四郎の体調不良もあり、岡三郎がボケ役に徹せねばならない事情もあったという)。
邦一郎がツッコミ、岡三郎が徹底的なボケ役となり、既に病気勝ちになっていた柳が時々喋るだけ――という往年のシャンバローからは考えられぬほど精彩のかけたものであった。
シャンバローの引き立てで芸術協会には入れたものの、活躍をする前に1982年11月頃、シャンバローは活動休止に入った。
1983年3月、三田宗司とコンビを組んで「ザ・ローカル」を結成。音曲漫才を展開した。
三田宗司の前歴
三田の経歴は『日本演芸家名鑑』に詳しい。高校卒業後の1962年、浪曲師の鹿島秀月の付き人となる。しばらくの間、浪曲師の前座的な扱いを受けて芸能界のイロハを磨いたという。
1964年、歌謡浪曲の鹿島ファミリー(鹿島伸月率いる歌謡漫談)に参加し、松竹演芸場などに出演。
当時のメンバーは鹿島伸月、昌子、弘、裕二――三田裕二と名乗っていたという。
1974年、ピン芸人をやっていた牛若と出会い、「弁慶と牛若」を結成。音楽漫才として高座に出るようになった。主に松竹演芸場を主戦場とし、季節ごとに出演するほどの常連であった。
この頃は、ギターと歌を使った純粋な音楽漫才だったという。
1978年、牛若とコンビを解消。「弁慶」の名義で音楽漫談家に転身、同年12月には早くも「弁慶」の名前で一人芸に移行している。弁慶時代は、ギターを片手にコミカル民謡やコミックソングを歌う芸であったという。
1983年初頭、シャンバローが活動休止して一人になっていた二代目岡三郎と出会い、意気投合。コンビを組むこととなる。つけた名前が「ザ・ローカル」。同年3月上席より芸術協会に入会し、寄席の高座に出るようになる。
ザ・ローカル時代とローカル岡の独立
岡三郎が朴訥な茨城訛りで時事ネタを振ったり、歌謡曲や流行語をボヤく。それに対して三田はギターを演奏して歌ったり、岡から「コワモテの人」と揶揄されて笑いを取る――という独特の音楽漫才であった。
桂文雀氏いわく、「三田先生は少し斜め後ろに立つ形でワキに徹していた」との由。
1991年頃、ローカル岡は後の相方となる佐々木晃彦と出会う。佐々木は回顧録『縁は異なもの味なもの~二代目桂小南からローカル岡の40年~』の中で――
今も変わりませんが、大相撲の千秋楽には相撲好きが贔屓の部屋に集まり、お相撲さんと飲み交わすのが恒例となっています。その打ち上げで、漫才をしていたローカル岡に出逢ったのです。飄々とした雰囲気で、「今度、浅草に出ますから来られませんか?」とのお誘いです。その当時、東京では、上野・鈴本演芸場、新宿末広亭、池袋演芸場、国立演芸場、そして浅草演芸ホールが定席と言われておりました。これらの寄席は、いつ行っても演芸を楽しむことができるからです。15年ほど東京を離れ、お笑い界に疎くなっていた私に、浅草は派手な身拵えで迎えてくれました。ありし日の浅草六区を偲ばせる数本の幟が揺れ、前座、二つ目の、呼び込む声が威勢よく響いています。木戸を通ると場内の笑い声が心地よく耳に入りました。
ザ・ローカルの漫才を楽しんで楽屋に伺う頃には、小南から薫陶を受けていた時代を思い遣るなど、“寄席の世界”の端くれ気分です。「そうですか、小南師匠を良くご存じなんですね」。話せば話すほど小南のお弟子さんなど、共通の知人・友人がいることが分かり気心は深まります。小南は落語芸術協会の理事職にあり、ローカル岡は本務がボーイズ・バラエティー協会でありながら“傑出の色もの”として芸術協会にも所属している芸人です。小南と私の関係を知ったローカル岡は、ギョウカイを知る人として私を、心腹の友と位置付けるようになります。
これ以来、佐々木はローカルの頼みで、ザ・ローカルの台本を書いて提供するようになったという。ローカル岡は佐々木の腕を見込んで、「シェンシェイ(先生)」と呼び、ボーイズ協会の面々を佐々木に引き合わせたという。
華々しい活躍こそなかったが、1980年代から90年代にかけて寄席と落語会を中心に活躍し、相応の地位を築き上げてきた。
しかし、三田は1990年代中頃より体調を崩すようになり、「ザ・ローカル」と看板こそ挙げながらも、高座には上がれない状態が続いた。
そのため、相方の岡が漫談や歌謡曲でつなぐような状態になった。
1995年、三田が病に倒れて、舞台に出られなくなったこともあり、独立。一方、自著『笑いのツボ押します』では、漫談家の独立を1994年としている。
1997年11月、「ローカル岡」と改名。芸名の由来は、「故郷の茨城県那珂市がローカル線しか通ってない」から、「ローカル」と、付けたという。ただし、芸人特有の自嘲もあるかもしれない。
以降、漫談家として活躍し、茨城訛りの残る独特の口調と鋭い批評やネタによって、人気を集め、遅咲きの大輪を見事に咲かせた。
なお、当人は「時事漫談」を十八番にしながらも「時事漫談って肩書は、じじいの漫談みたいでイヤだ」という不思議な美学を持っていた。
1999年7月31日には、経済学者の佐々木晃彦とコンビを組み、「ローカル岡・晃彦」の名義で、「お笑い講義」と称して各寄席に出演した。
一方の三田は2000年代に入り、復帰は困難と考えたのか、2003年12月末を持って芸術協会を退会。これと共に芸能界を去った模様。
この引退を機に、ザ・ローカルは事実上の解散となった。
2004年9月12日、ローカル岡は60歳にして笑点に初出演し、時事漫談を披露している。この頃からジワジワとブレイクをはじめ、各演芸番組やバラエティ番組、寄席の名人会に呼ばれるようになった。
晩年の話術は業界人にも高く評価され、高田文夫は『毎日新聞』(2005年6月9日号)のエッセイの中で「ローカル岡は最後の“寄席の色もの”かも知れない」と激賞している。当人も高田文夫に会うたび「シェンセー(先生)のおかげで勇名になれました」と照れながらいつも感謝の弁を述べていたという。
2005年10月、自身のギャグや漫談をまとめた『笑いのツボ押します』を出版。これが遺作のような形となってしまった。この頃から体調不良に悩まされたそうで、闘病をしながら高座に出ていた。
2005年12月11日、最後の気力を振り絞って「笑点」の収録に参加して漫談を一席演じた。
同年12月20日、自宅で大量喀血し昏倒、緊急入院となった。
それからひと月足らずの1月16日、肝硬変のために新宿の病院で死去。62歳の若さであった。
生前の勇姿は2006年1月29日の笑点で放映された。その際には追悼のテロップが入れられたそうで――
追悼ローカル岡 茨城なまりの独特の語り口で人気だったローカル岡さんが、1月16日肝硬変のため亡くなりました。62歳という早すぎる死を悔やみ、2005年12月11日に収録してあった笑点最後の舞台を、本日はお送りします。
という旨が流れたという。笑点でも珍しい追悼テロップではなかったか。