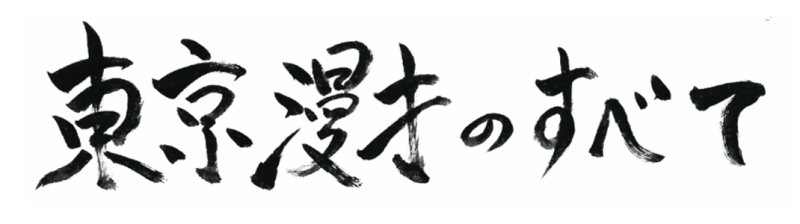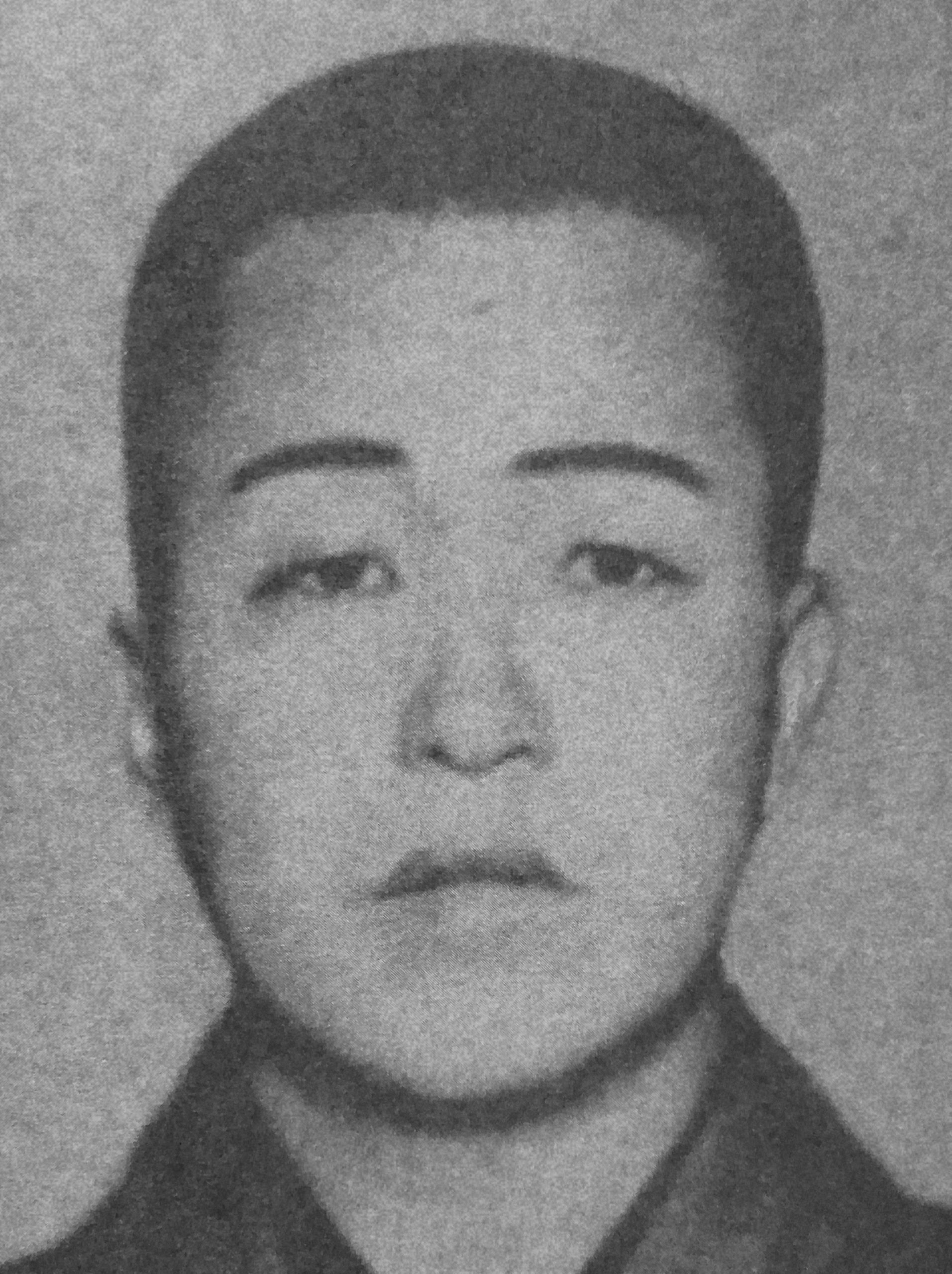日の出家笛亀
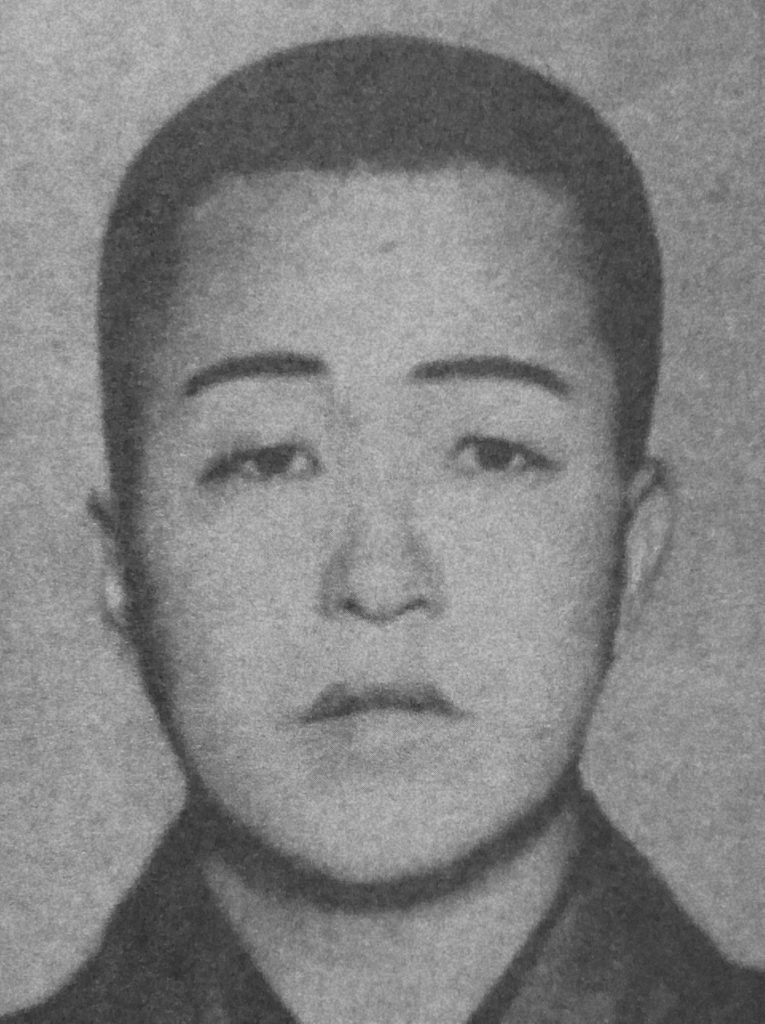
若かりし頃の笛亀
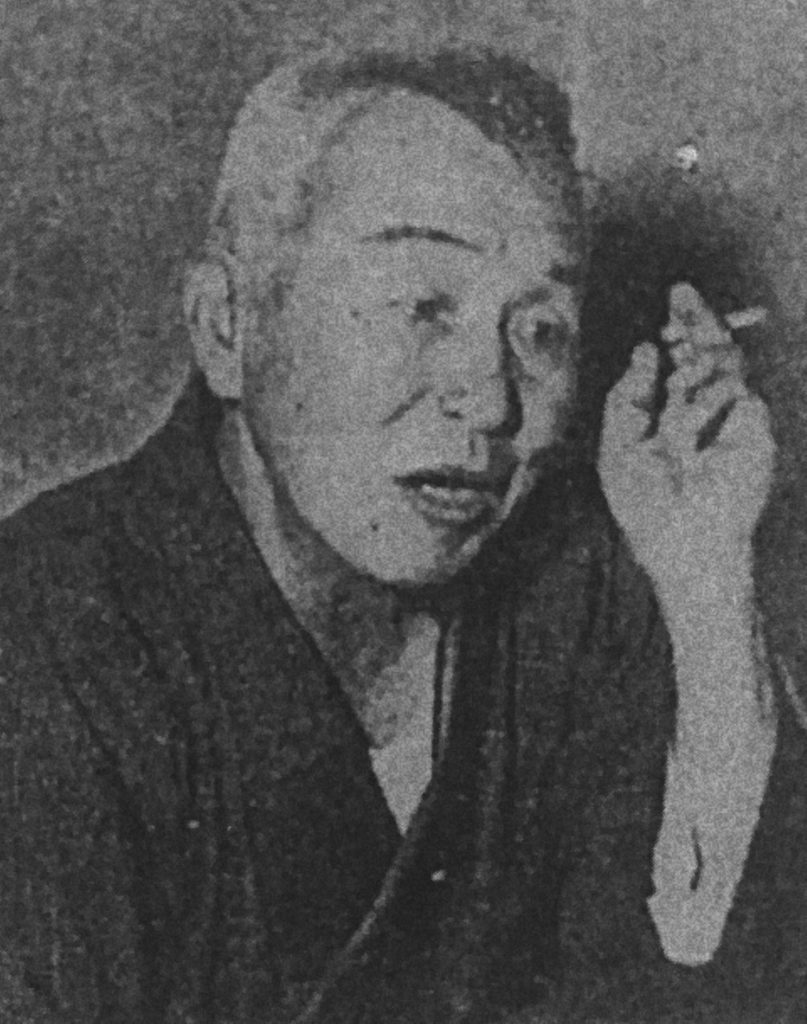
晩年の笛亀
人 物
日の出家 笛亀
・本 名 亀井 峯一郎
・生没年 1895年3月13日~1957、8年頃
・出身地 群馬県 太田市
来 歴
戦前戦後活躍した漫芸の名人。日の出家笛亀とも書く。笛の曲弾きを得意とした。区分的には漫才師ではなく、雑芸色物であるが、漫才師たちと交友が深く、吉本興業との関係も深かったため、特例として挙げておく。
その前歴は大槻三好『石原和三郎と明治唱歌抄』と『八木節考』、『朝日新聞栃木版』(1936年1月12日号)の談話に詳しい。以下はその記述をまとめたもの。
出身は群馬県新田郡鳥之郷村鳥山(現・太田市)。博労・亀井清三郎の長男として生まれるが、この清三郎が大変に大酒呑みであった為に、妻と子供に愛想を尽かされ、早くに生き別れている。妹に、亀井とりという子がおり、この子は後年、埼玉の蕨へと嫁いだ。
家長と離れ離れになったことにより、当然家は困窮し、鳥之郷小学校を中退し、村の名士である飯田一家の下へ奉公に出る。
この頃、村に来る楽隊の音色に魅せられ、横笛を吹くようになったという。
飯田家に数年勤めた後、山田郡矢場川村矢場の地主、相場家の作男として働くようになる。この矢場川村の隣が堀込源太の住む村だったため、堀込源太と面識を持つようになる。
話が逸れるが、八木節は栃木の民謡、群馬の民謡とやたらに揉めたがるが、こういう境界線の曖昧さを指摘しておかねばならない。やたらに栃木のものという論調が目立つが、その元ネタは群馬にあると思うとなかなか複雑なものである。いつの世も、宗家争いの種は尽きまじ、か。
この頃から、堀込源太の一座に出入りをしては横笛を吹いて、八木節を覚えた。笛の腕前はますます上がり、いつしか「笛亀」と呼ばれるようになったそうな。芸名は多分「笛の亀井」というような渾名から名付けた模様か。
その内、芸人に志を抱くようになり、故郷を奔走。さる田舎周りの劇団に入り、「新井一雄」なる二枚目風の芸名で舞台に立つようになる。同劇団の名は伝わってないが、喜劇、人情劇、壮士劇と何でもありの一座だったらしく、ここで色々な芸を仕込んだ。
しかし、ドサ回りの一座であることには変わりなく、北海道旭川市の錦座で興行中、劇団に見切りをつけてドロン。然し、すぐさま路銀が尽きて乞食同様の日々を過ごすが、船頭さんの情けで安物の笛を買ってもらい、その笛を吹いて投げ銭をもらい、東京まで戻る旅にでた。
ひどく苦しい、陰惨な旅だったそうであるが、この中で横笛の極意と志に目覚め、開眼。この経験が後の名人芸へとつながったという。
朝倉喬司『流行り唄の誕生』の中に詳しく出ているので引用。
旅まわりをかさねた末、役者としての将来を見限った彼は、北海道の旭川で一座から逃走する。 懐中無一物。渡船場の船頭さんの情で笛を買ってもらい、投げ銭目当ての乞食道中。ある山道に行き暮れて、すきっ腹をかかえ、木の葉をかぶって寝ていると、赤い着物の老人がマクラ元で横笛を吹いていた。ところが響くのは尺八の音。神様に出会った気がした彼は、起き出して自分の笛を吹いてみた。すると今までとは全くちがった、美しい音色が出た。ここで彼は横笛と尺八の“たすきがけ”奏法に一念発起し、旅をつづけて上京、源太一座に加わったのだった。
こうして、源太チームの顔ぶれをみていくと、それぞれ、共同体の包摂する時空から微妙に身をズラし、間合いをはかりながら、歌にいきついた人たちであることがよくわかる。天才・笛亀にいたっては、ほぼ“外部”の人になりきった上で内側へ一直線に突入してきた趣きだ。さまざまな形をとった彼らの周辺性が、八木節を東京で成功させた最も大きな要因だったと思われる。
90日近く歩き続けてやっと東京へたどり着き、浅草で人気を集めていた堀込源太と再会。すぐさま一座に入れてもらって、笛を担当するようになる。
ちょうど八木節ブームの真っ只中とあって、1920年、堀込源太が引き上げるまで、長らく浅草の劇場の顔として人気を集めたという。
この頃、若かりし頃の前田勝之助などと出会っている。
その後は、堀込源太から独立して東京へ残留。笛芸と漫芸を武器に「笛亀」の看板を掲げるようになった。
しかし、震災などに遭遇したため、東京を離れ、一座を結成。故郷の群馬へと戻り、錦を飾る名披露目興行を打った。
「鳥之郷村に隣接した治郎右衛門橋の旭座で興行することになり、二十七名の座員を引きつれ、停車場に着いたら迎い花が七つ、昔のいたずら友達から幟は出るし、街まわりの屋台は村の若衆がかついでくれるし、旭座は大入り満員だった」
と、「八木節考」の中で、回顧するほどの大当たりを取り、次から次へと興行師が訪れて、一時は2000円の札束を掴むほどの絶頂にあったが、新潟巡業へと足を伸ばしたのがつまずきのはじめであれよあれよという間にご難が続き、あっという間に800円の借金をこしらえてしまった。
結局、座員を手放し、衣装やかつら、身の回りの品まで差し押さえられ、借金苦のどん底へと突き落とされる。
ここで『八木節考』などでは、一座解散の憂き目にあったものの、吉本興業部が拾い上げてくれた――と簡潔に書いているが、実際は太神楽の日の出家潮三郎と手を組んで、太神楽・音曲などを武器に、寄席や劇場に出演していたのが実情のようである。
日の出家一門と懇意だった事もあってか、「日の出家笛亀」と名乗った。
この日の出家潮三郎という人は、本名「鹿島昌生(潮三郎という文献もある)」。明治22年5月25日生まれ。『富士』(1932年新年特大号)では「師匠なしの独学」とある。
一方、『日本太神楽辞典』などを読むと、元は前橋出身の太神楽だったそうで、群馬県下で人気があったという。そういう関係で笛亀とも仲が良かった、と考えると納得できなくはない。笛亀同様に、吉本興業に所属して、長らく人気を集めたという。
昭和に改元以降はどうも独立したらしく、万成座や寄席に出るようになったそうで、『都新聞』(1930年1月31日号)に、
▲萬成座 一日より安来節宗子駒奴一行、染團治、雅子、〆奴、市丸、捨奴、笛亀、壽賀若、文蝶、孤遊新加入
などとあるのが確認できる。
吉本へ本格的に参加したのは、1928年頃だろうか。『上方落語史料集成』掲載の『大阪時事新報』(5月2日号)によると、
◇紅梅亭 吉本興行部専属万歳秘技競演会 出演者はセメンダル・小松月、玉枝・成三郎、愛子・光晴、楽春・久春、二蝶・芳春、日佐丸・弥多丸、しの武・次郎、カチユシヤ・ラツパ、芳香・芳丸、今男・アチヤコ、大正坊・捨次、ウグヰス・チヤツプリン。余興笛亀、幸治、李玉川。
とあるのが最初の模様か。以来、度々関西へ行っては、吉本興業直轄の劇場に出演。『上方落語史料集成』を覗くと、年に1~2月ほどは関西の寄席に出演している。
1927年3月1日より、浅草凌雲座に出演。『都新聞』の広告に、
▲凌雲座 一日より中村種春、壽家岩てこ、大津三八二、港家奈美江、笛亀、少女歌劇等加入出演
1927年4月、引き続き凌雲座に出演。同月25日、歌人の斎藤茂吉が凌雲座に赴き、その舞台を見ている。『斎藤茂吉日記』の中によると、
4、浅草観音ニ詣テ、すしヲ食フ。凌雲座ニユキテ安来節ヲキク。笛亀ト云フ男ハ昔、八木節時代ノ男ナリシガコノゴロ笛ヲ吹クナリ。ソノ男ハシマヒニ八木節ヲヤツタ。ヤハリナツカシイ。
『斎藤茂吉全集第46巻』363頁
1928年3月、遊楽館に出演。当時の広告に、
安来節美人連 勝代 花龍 殿子外大勢
オナジミノ變骨万歳 大和家秀夫・秀千代
浮世節 東家駒之助
◎初御目見得◎ 万歳界の驚異!! 所作事・三曲万歳 丸八大一座
抱腹笑倒 吉野山千本桜
全女流万歳の覇王名妓 竹廼家小奴・小蝶
横笛名人 笛亀
米国帰朝モダン 文化万歳 轟一蝶・浪速家日出子
1928年10月、東京へ戻り、浅草劇場へ出演。
1928年10月24日、JOAKの放送『雑曲情緒』に出演。『都新聞』のラジオ欄に、
さてその次はお待兼の笛龜こと、龜井健一郎君の笛道楽だ、笛龜は肥つた身體に、五六本の笛を前に、あご髭をチョツピリとはやしたにこやかな男だ 笛を布で拭ながら一寸吹いてみる――いゝ音だ「鳴る、鳴る――商賣とは云へ、どうしてかう綺麗だらう」などゝ自分で自慢して笛に口を當る、先づ最初は八木節だ、合いの手のピッーピツーピッピキピーといふ處が馬鹿にいゝ、安来、小原と進んで来て追分では尺八の太い音を出す中々器用な男だ、最後は春雨でしつぽり濡れかゝる
と紹介され、『読売新聞』では、
續いて出るが龜井健一郎さん、この人は長らく大阪へ行つてゐてツイ十二三日前に東京へ舞ひ戻つたばかり、目下浅草劇場に出てゐる笛龜さん其の人で、酒を飲まなければ舞臺へ出られないといふ位の有名なのんべだが一本の笛でドンナ歌でも吹き分けるといふ笛の名手『春雨』から始まつて小原節と進み吟聲に變つた味を出した最後に八木節を聴かせて引き下がる
と紹介されている。当時の消息が記されていて貴重。しかし、微妙に曲目の順が違うのはどうなっているのだろうか。
1929年5月、パーロフォンより「詩吟・春雨」(1039)を発売。
吉本が東京へ進出したあとは主に浅草花月を中心に活躍。その名人芸は高く評価され、名人会や落語の色物として度々出演している様子が確認できる。
笛亀の十八番は、横笛を吹きながら尺八の音色を出す芸で、これは名人芸と高く評価された。それ以外にも流行歌を吹く、浪曲師や義太夫節のクセを見事に吹き分けるなど、雑芸の領域を超えた力量に、定評があったという。
また、笛を吹く前にボヤく話術も人気があったそうで、ある意味では、立花家扇遊などと並ぶ異色の存在なのかもしれない。
一方、なかなかずぼらな所もあったようで、酒を飲んで泥酔しながら高座に上がる事も多々あった。そうした一面もに人気があったらしい。『宝生』(1941年3月号)掲載の宝生英雄を囲む座談会の中で――
市村 浅草に笛亀といふ名人がゐましたね。
宝生 あゝ、寄席へ出てゐましたね。
市村 酒を飲んでベロン/\になつてゐても高座に上つてもう一杯ぐつとやつて唄口をしめすと、シャンとして、顔が芸人らしいいゝ顔になりました。
宝生 大変だったさうですね。焼酎でせう。
と茶化されている。
一方、浅草では相当の顔役だったそうで、浅草通いの文人にも愛された。
ノーベル文学賞作家の川端康成は若き日の傑作『淺草紅團』の中で――
横笛吹きの笛亀は、遊樂館の舞台で、さんざ悪態をつきながらも、彼の罵るジャズ小唄を吹かなければ、十分に客の手をいただけないのだ。
と、その悲哀を記している。演歌の父、添田唖蝉坊は『浅草底流記』の中で「笛亀の、あごひげを愛せ。」と記している。
また、寄席芸人だけではなく喜劇役者とも付き合いがあった。『都新聞』(1935年2月9日号)に、
横浜大久保の福由奥座敷で、曾我廼家〆太郎と笛亀が部屋を締切つて密議をこらしてゐるので何か重大な計画でも――と小清小秀のグループが忍び足で様子を探ると、何んのこと、サノサ節の歌詞の内「ね」の字をぬいて小唄に仕上げ、これを〆太郎節と命名して近く流行らせようとの打合せ、芸妓連呆れて、非常時サノサね
1940年、帝都漫才協会再編に伴い、新設された全藝部に入部し、同会の幹部に就任。『都新聞』(1940年9月22日号)に、
漫才協會結成 クスグリも國策極力 各自の生活も刷新
警視廳統制下の技藝者團體の一翼たる帝都漫才協會は廿一日午後十時より浅草松屋六回特別食堂を會場に創立総會、續いて發會式を挙行、新體制の○足を踏出したがこの傘下に集まる漫才實に四百三十餘名、大久保源之丞を名誉會長に、戸村禮文氏を相談役に、會長以下の役員は次の通り選任された
(會長)林家染團治▽(副會長)大朝家五二郎、大道寺春之助、千代田松緑▽(會計)玉子家源一、前田勝之助(理事)天津城逸郎、荒川小芳、桂喜代楽、浮世亭銀猫、砂川捨勝、小櫻金之助、松島家圓太郎、勝昌介、松尾六郎、小山慶司、荒川清丸
なほ漫才ではない曲技、漫藝等も更にこの協會の一翼として全藝部を組織、この會員五十名、その理事として日の出家笛亀、曾我廼家祐十郎、桂一奴の三名が選ばれた、ところでこの漫才協會が採つた新體制的な仕組といふのは殊にもこれからの漫才は、舞臺にあつては常に国策順應の心構へを忘れないと共に下品なクスグリや卑猥な藝を避け、舞臺外にあつても世の指導を受けるやうな生活をして行かなければならないのは言ふを佼たたないが、それには従来のやうな○○○や○○○の選示にはかり頼つてゐては効果が挙らないといふ譯で案を優つた結果、全會員を地域的に十二部に分け、これに前記十一理事と會計係の玉子家源一を加へた十二名がそれぞれ部長となつて、自分の部に属する會員達の行動共にそれの責を任じて、他部に負けないやうにして行かうといふ譯で、この効果に對しては、○○も相當期待を掛けてゐるやうである
1943年、帝都漫才協会が、「大日本漫才協会」へと改称するにあたり、「相談役部長」に就任。全芸部の部長は、桂一奴であった。
戦時中は、浅草の劇場や慰問で活躍していたが、戦災や劇場の閉鎖で、敗戦前後は地方巡業などをして、細々と暮らしていた模様。
1949年秋、かつての知り合い、飯田明治の招きで群馬に戻り、笛芸を披露。これが芸人としての最後の帰郷だったのではなかろうか。
晩年は安来節の木馬館を中心に、活躍を続けた。老いてなお、笛芸の音色は冴え渡り、評判を集めた他、戦後長らく不足していた好きな酒も買えるようになって、細やかながら安楽な日々を送っていた。
晩年の高座と人気ぶりは『アサヒ芸能新聞』(1954年6月1週号)掲載の松浦善三郎『関東芸能人斬捨御免』に詳しい。以下はその引用である。
日の出家笛亀(横笛) 興行ビラにもかならず日本一横笛の名手と書かせる。幕内でも大先輩。机上に愛用の横笛数本をならべて、歌により調子によってそれぞれ別々の笛をとりあげ、いまはなつかしい江戸弁でちょっといそがしそうにシャベリながら客を笑わせる。笑わせておいてさっと急テンポに笛を吹く。その呼吸のうまさはやはり日本一。横笛といえば今日では一般には神楽ばやしかなにか特種な機会にしか接しられなくなってしまったがこの人はこれを寄席芸術に発展させた人。したがって曲も港シャンソンあり、 湯の町悲歌あり、聴くものをして笛の音色の美しさとともに、表現の偉大なのにただ感嘆せしむるのみ。「家に帰って一ぱいやるのが楽しみで」といいながら、横笛に一生をささげるとの名人に幸多かれと祈る。放送局はいまのうちに録音の要あり。
多くの芸人が脱落、廃業する中で、これだけの人気と地位を保てた人は珍しいのではないだろうか。
ただし、当人は後継者の問題など、悩みを抱えていたそうで、複雑な二面性が伺える。
後継者不足や流行の変化は、名人気質の彼にとって癪だったとみえて、最晩年、『内外タイムス』(1954年10月24日号)でこんな事をボヤいている。
寄席芸人 ちょっと一言
「もういけませんや、天下の笛亀もアッシ一代でおしまいでさァね、当節の若いもんは修行が足りねえし第一辛抱ができませんや、やれジャズだ、ダンスだなんてね、アッシだっえ何もこれまで売った笛亀なんだから、一代でつぶしたくはねえんですぜ、それでももうアッシがいけませんやね、このトシになって弟子で苦労はしたくねえわけでさァ、まあ考えてみればシャクにさわることばかりでね、楽屋に第一礼儀がねえからヒデエもんで……先輩も後輩もあったものじゃなしね、アッシらが羽二重の下着で上る舞台にも土足で上るんだから、まるっきり茶ブ台に足のっけて飯食ってるようなもんでさァ、それで通る世の中なんだからアッシがいくら便所で”キンカクシ”につかまって男泣きすることがあっても、二代目をつくろうとしない気持もわかろうじゃねえですかい」と艶々とした顔を紅潮させて彼はいうのです、そりゃそうでしょう、彼の芸界の半世紀には、日本の変転がソックリ含まれているのですから、六十歳の笛亀さんが何もかも気に入らないのも無理はないのです
「昔はよかったねェ、舞台でくだらないことをやると、かえってあいつは”イキな芸人”だなんていってくれてね、お客もイキだったよ、それがどうでえ、今の客は、アッシの芸がわかるのは二人か三人だよ、苦労して”ジョールリ”なんか笛でやってもポカンとしていやがる、やたらにきつく鳴ればいいと思ってるんだね、ヘン笑わせやがらヘヘへ」寂しそうな笑い声なんです、年期を入れて苦労して、心からの芸人の彼には、今の浅草が不思議で仕方ないらしいのです
「江戸見物っていえば浅草だァね、まずカンノン様よそれから花屋敷で十二階さ、最後に江川のタマ乗りでものぞいて、あゝ江戸を見たッ手なもんよ、それがどうでェ今の浅草はハダカの娘ッ子見てニタニタばかりしやがって、いけねェね、世の中がまるっきり変ってるもの、やっぱり古いというのかね、アッシの方がーーテケテンテンピーヒャラヒャラリなんて馬鹿ばやしや八木節の笛が一番受けたりしてね、芸ッてものは難しいもんだけどね、本当に芸術だよ、”術”だからね」と重ねて芸術を強調するのでした、舞台からは同じように芸術の安来節が聞えてきます、この笛芸術の彼はウットリと目を細めてきゝいっているのでした
この談話が、ある意味での遺言という形となったとみえて、その数年後に倒れ、まもなく死没。
詳しい没年は不明であるが、『太田市史』によると、1957年とも58年ともいい、享年は63歳くらいだったとの由。
親戚には亀井五作というのがおり、この人が亀井の生家を守ったそうで、この人の話では「上野に墓がある」とのことである。