東亭花橘・玉子家光子

杵屋臼五郎・住吉家杵丸時代の二人

餅を搗く二人
人 物
人 物
東亭花橘
・本 名 渋谷 庄九郎
・生没年 ??~1964年以降
・出身地 島根県?
玉子家 光子
・本 名 渋谷 光江
・生没年 ??~1964年以降
・出身地 島根県?
来 歴
高座の上で餅を搗き、曲芸を見せる芸を売り物にした異色のコンビであったという。今、臼と杵と漫才師といえば、クールポコのような芸を考えがちであるが、どちらかというと大道芸の「曲搗き」に近いものであったそうである。
このコンビの前歴はほとんど分からない。多分、他の芸から漫才へと転向したものだと思われるが、当時、最早廃っていたであろう曲搗きなど、どこで覚えたのか知らん。
「曲搗き」は、元来粟餅を売るために客寄せで演じられた芸であり、その流れを辿ると、江戸時代の生玉屋正六にまで遡れる。
「近世商売尽狂歌合」七番右に、この曲搗きの様子が紹介されているが、滑稽な戯れ唄とダイナミックな臼と杵の曲芸を売り物にしたようで、大変な人気だったそうである。
コンビ結成
コンビ結成年も分からないが、古いのは確かである。
1925年には上京を果たしており、1925年12月21日付の『都新聞』の広告に、
▲三幸劇場 安来節大會番外として初上京の安来杵丸、臼五郎が廿日より加入安来名物「餅の曲搗」を出す
その頃は、「安來臼五郎・安來杵丸」と名乗っていた模様である。翌1926年1月2日付の『都新聞』の広告に、
浅草三幸劇場
出雲ろく
出雲八重
出雲いと
大合同安来節大会新加入
安来杵丸 安来臼五郎 玉子家利丸
という記載がある。後年、「杵屋臼五郎・住吉家杵丸」と改名した模様か。
以来、浅草の常連出演者となったと見えて、劇場に進出。安来節一座に留まらず、演芸会などにも出演した。1927年2月2日付の『都新聞』にある、
▲凌雲座 華嬢経営は一月限りにて二月より松島興行部で経営し各派大演藝會で開場出演者は 初代梅坊主一座、春本助次郎、寶家和楽、港家奈美江、萬歳加藤瀧子、杵屋臼五郎、福本連、染團次、天路幸二、二代目岩てこ
などはいい例であろう。暫く東西を行き来していた模様であるが、間もなく本格的に上京し、東京に定住した。
1933年元日、『都新聞』に掲載された、浅草の劇場「三友館」の連名の中に、「東亭花橘・住吉家杵丸」とある。この頃に東亭花橘と改名した模様か。
東京漫才の良き理解者であった作家の玉川一郎は連載「よみうり演芸館」(「読売新聞・夕刊」1960年2月9日号)で、東京漫才の元祖・東喜代駒と、都家福丸・香津代の名前を出した上で、
いま、モチの曲搗き(きょくづき)をしている杵屋臼五郎、杵丸もそのころは東家花橘、光子でやっていったというが、もう少しあとになるだろう。
と、記している。
また、手元にある「大衆芸能資料集成」を読んでいたところ、
昭和三年道頓堀における萬歳大会
松竹専属大一座 全国萬歳名人大会
弁天座 昭和三年二月二十一日(三月七日まで日延べ)寿家岩てこ・中村種春
橘家菊春・太郎
住吉家杵丸・杵屋臼五郎
……
という記載を見つけた。この杵丸・臼五郎というのが、前身である。
戦前は餅つきの花橘と鳴らしただけあってか、中々の人気があったそうで、特に、選ばれた芸人しか出ることのできなかった「東宝名人会」への出演したという記録を見ると、その人気ぶりの片鱗を伺い知れると共に、人気の証明となっている。
初出演を遂げたのは、昭和11年12月のことで、漫才師が初出演をした順からすると、五本指に入る程の早さである。(一位は昭和10年7月に初出演を遂げた喜代駒と浪速シカク・マンマルの二組。その後、春風枝左松、東亭花橘と続く。)
「東宝名人会」を主催していた秦豊吉は、自著「昭和の名人會」の中で、
歳末なので、東亭花橘社中が、餅の曲つきという賑かな一場を作つた。三味線に合せて、餅つきをする振である。
と、その存在を明らかにしている。歳末のムードに合わせて、花橘社中を呼んだ秦豊吉とは何と粋な人ではないか、と言いたくなるような位、心憎い演出である。
戦時中と吉本時代
戦時中は、その人気と賑やかな芸風が買われたのか、吉本と陸軍恤兵部が行っていた戦地演芸慰問団の「わらわし隊」に招き入れられ、第4回わらわし隊の一員として、北支を回っている。
早坂隆の『戦地演芸慰問団「わらわし隊」の記録』によると、この時のメンバーは、
北支那慰問班
河内家美代次・文春、東亭花橘・玉子家光子、大利根太郎(曲師 吉沢団蔵)
中支那慰問班
桂金哉・金二、祇園千代子・砂川捨勝、木村小友(曲師・戸川大助)
南支那慰問班
千代田みどり・松緑、林家染子・染次、広沢小虎造(曲師・とし子)
艦隊慰問班
柳家千枝造・漫作、奥野イチロウ・竹本ジロウ、秋山右楽・左楽 浪花軒〆友(曲師・荒川文柳)、松平晃(アコーディオン・岡本豊久)
(同著 348~9頁)
(註・資料の記録された当時の情勢や資料の引用上の関係から、支那と記しておりますが、決して差別を助長するものではありません。ご了承ください。)
と、4班に分かれていたようである。第1、2回の時は、花菱アチャコやミスワカナなど、関西の漫才師が大体を占めていたが、この回では東京の漫才師が多数を占めており、大変に興味深い。その頃の東京漫才の勢いと人気者の様子を垣間見ることが出来るような気がする。
なお、わらわし隊は吉本興業所属の人材が主に送られたので、ここに記された面々もまた東京吉本の所属だったに違いない。
(喜利彦余録 回りくどい書き方をしたが、実際に東京吉本の所属であったという資料は残っており、一度見た事がある(未所有ではあるが)。手元にあるメモによると、「吉本笑ひの共栄圏渋谷進出」という宣伝と共に、「東京吉本直属技芸士一覧」という名簿が出ており、その中にこのコンビの名も出ている。一応、他の芸人と共に、掲載する事にする。)
東京吉本直属技藝士一覧 漫才 (順不同)
林家染団治・高山美貴子、千代田松緑・千代田わかば、都路繁子・立花六三郎、桂里子・桂文弥、玉子家光子・東亭花橘、河内家芳江・桂三五郎、河内家美代次・河内家文春、林家染次・染子、林實・町田武、西山奈美江・大倉壽賀若、松平漫謡隊(松平操?)、橘家菊春・橘家太郎一行 (以下略)
また、面白い所では、戦時色が世相を支配するようになった昭和18年の『讀賣新聞・夕刊』(昭和18年8月20日号)に掲載された「決戦隣組銘々傳(三) 漫才隣組」という記事の中で、このコンビの名前を確認することが出来る。
――人呼んで”漫才隣組″といふ、こゝは浅草區田島町の第四十六隣組、歓楽境浅草にほどちかい藝人街が田島町だ、浪曲家あり、落語家あり、義太夫語りありの真ン中で一きは目立つのが組員の殆どが漫才業だといふ第四十六隣組だ、組長の河野春雄(43)さん=藝名市山壽太郎=一家をはじめ酒井義二郎、山路春美、東亭花橘、玉子家光子……と數へあげたら九人が漫才業、ほかは大和家姉妹ら藝人で占められその十九世帯六十八人が組長のもとにガツチリと一致團結してゐる。
戦後の動向
敗戦後も漫才師を廃業することなく、それなりの人気があったようで、「読売新聞 朝刊」(1946年9月20日号)に、
第十九回 よみうり野外芸能会
けふ正午開演 日比谷旧音楽堂(入場無料)
秋まつり
◇太神楽 翁家喜楽
◇漫才 玉子家光子、東亭花橘
◇落語 三遊亭円楽
◇舞踊(特別出演)清元「夕立」市川紅梅、清元千代太夫、梅助他雨天中止 主催 読売新聞社
なる記事も確認できる。
だが、その活動も余りは長くはなかったと見えて、進駐軍の慰問や東京吉本の撤退などを理由に、漫才から曲搗きショーへとシフトを変更した模様である。以来、浅草の松竹演芸場や余興などで中々人気を集めたそうな。
1957年1月2日には、東亭杵五郎という名義で、OTV(大阪テレビ)の番組、「名人会」(13:00~)に出演していることが判明している。この時の共演者は、桂文楽、小唄勝太郎(川崎隆章「まぼろしの大阪テレビ ~1000日の空中博覧会~」184頁より)。
その時の外題はずばり、「餅の曲搗」。昔取った杵柄である、古風な曲搗を見せていたものと推測できる。
1963年度の電話帳の中に「東亭花橘」とあるのが確認できる。相当息が長かったようである。
しかし、その後は何をやっていたのか分からず、手元にある極楽寺の名簿にもその名前は記されていない。徹頭徹尾、素性のよく知れないコンビである。
芸 風
文中で何度も繰り返すように、餅の曲搗が何といっても看板芸で、これ以外の芸は特に伝わっていないので、杵や臼をジャグリングのように扱い、器用に餅を搗く素振りを見せていた、としか言いようがない。
その芸の様子を端的に表したものとしては、先述した秦豊吉の文章と、波多野栄一の回顧(「寄席と色物」)が、あげられる。尤もそれしかないと言われるとその通りなのだが……。
東亭花橘・光子 餅つきの花橘といンて三味線や鳴物で賑かに高座で餅をついた
今からすると、高座で曲搗をするなど、どんな神経をしているのかと思うかもしれないが、トランペットを吹きながら前に倒れる芸をやる漫才師や、曲芸をやる漫才師、果ては、蠅や蛆虫の物真似をする漫才師もいたことを踏まえると格段驚くべきことではない。
当時の漫才の芸種の広さ、貪欲さは現在の比ではなかった。このような諸芸と雑多の中から、現在のような漫才が洗練、発展を遂げて生れてきたことを忘れてはならない。
最後に、江戸時代に行われた「曲搗」の芸や所作を偲ぶために、「近世商売尽狂歌合」の、一節を引用することにしよう。猥雑な文句であるが、ひなびた味と洒脱さがあって面白い。
七番右 粟餅曲番
名代々々 これはお江戸で御評判の いくだまや正六の家の看板あわ餅の きょくつきじや ソリヤ つくヤレ つくゝゝゝゝ なにをつく 麦舂(つく)米つく 稗をつく 証文手形に判ンをつく 旦那のしりへ 供がつく 女郎はお客のゑりにつく 朝のわかれに山寺のゝゝ ずんぼら坊主かねをつく たきつく うそつく くらいつく 居ざりの きんたま砂がつく サツサ コレハ 根元なだい ゝゝゝ
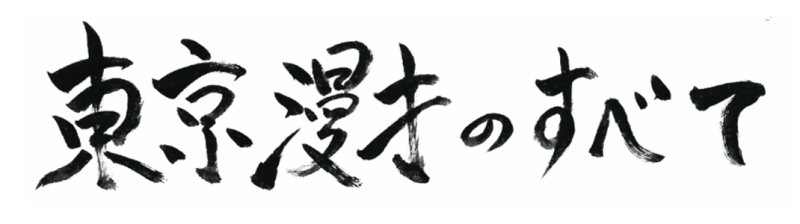


コメント