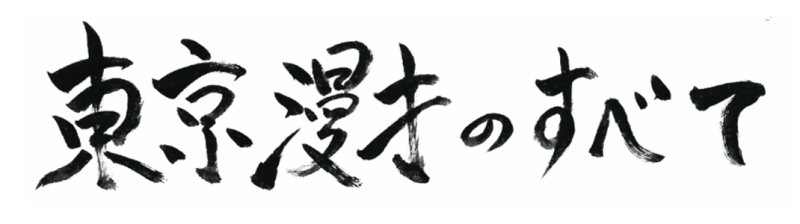昭和のいる・こいる

漫才コンクール優勝時の昭和のいる・こいる(真ん中)

昭和のいる・こいる(左)
人 物
昭和 のいる
・本 名 岡田 弘
・生没年 1936年7月23日~2025年5月24日
・出身地 石川県 石川郡 吉野谷村
昭和 こいる
・本 名 庄田 太一
・生没年 1944年1月26日~2021年12月30日
・出身地 群馬県 伊勢崎市
来歴
来 歴
「ヘーヘーホーホ」「よかったね、よかったね」の相槌漫才で知られた昭和のいる・こいる。
2021年に昭和こいるが死去し、のいるだけが生き残っていたが、2025年5月26日、のいるの訃報が掲載された。
東京漫才の大スターとして各紙に訃報が出ているが、情報の錯そうが激しいので、ここでまとめる事にした。供養になれば幸いである。
昭和のいるの前歴
昭和のいるは「石川県石川郡吉野谷村字市原」という山奥の出身。実家は大工と農家と製材所というすごい家であった。
なお、一部文献では「1942年7月23日生まれ」とあるが、実際は「1936年生まれ」である。のいるが獅子てんや・瀬戸わんや門下へ弟子入りする際に「昭和11年を17年に間違えられた」といい、「お前は若く見えるから17年生まれの方が周りに親しまれるだろう」という師匠の配慮があった。
このことに関しては当人が『東京かわら版』(1999年6月号)の聞書きの中でしっかりと明言している。
のいる ぼくは昭和十七年の生まれということになっているんですが、本当はもっと年なんです。還暦過ぎてるんですよ(笑)。
弟子入りしたときに、履歴書に「十一年」と書いたらそれが「十七年」に見えたんですね。「いいよ、お前はどうせ若く見えるんだから」と言われたので、そのまま…(笑)
ぼくはこの世界へ入るのが遅かったんです。二十九歳で入りましたから。
石川の田舎に育って東京へ行くまでの経緯は『東京かわら版』(1999年6月号)の聞書きに詳しい――
のいる 親父は大工、おふくろは農業でした。うちは一人一人みんな違うんです。じいさん(=祖父)は製材所をやっていたんです。
小さい頃はわんぱく坊主でしたね。マジメじゃなかったですね。いたずらもしたし……。
こいる 野山を駆けめぐって(笑)。
のいる (背が)小さいでしょう。昔から小さいんだから(笑)。並ぶときはいつも一番前で、前から二番目になったのが最高記録でした。
小学校と中学校が一緒で、吉野谷村立市原小中学校。生徒の数は百八十人ぐらいでした。
一学年一クラスで、三十一人でした。男十六人ぐらいだったかな。やっぱりクラスの中だけの生活で、上級生を好きになるとか、下級生を好きになるなんてことはなかったですね。
ぼくは教師になろうと思って東京へ出てきたんです。
国士舘へ入ったんですが、ここへ入ろうと思って一生懸命に勉強したわけじゃないんです。
ぼくはその時その時で、ホント、刹那的な生き方をしているんです。入試要項を見たら、英語の試験が無かった(笑)。で、教職課程があったから。
英語は苦手も苦手、もう……。
こいる 昔、代用教員というのがあったんです。
のいる (国士舘に入学する前)高校を卒業してすぐに、吉野谷の村の分教場の代用教員になったんです。それを二年ぐらいやってから教員になろうと思ったんです。
こいる 分教場だから生徒の数もそんなにいなかったんじゃないの?
のいる うん。本校になると百何十人いたけど。
臨時の教員だから、よく言うけど、日教組にも入ってなかったんです。
それで、東京に出てきたのですが、井の中の蛙大海を知らず、東京があんまりすばらしい街なので、 学校なんかどっちでもよくなっちゃった(笑)。
大学で遊び惚けた末に「こんな大人に教育を教わるとは子供も可哀想だ」と教育課程も取らずにそのままダラダラと進級、学位だけは取った。
大学卒業後は工事現場のバイトをしていたが、すぐに離職。ブラブラしていた時に歌声喫茶に誘われることとなった。聞書きでは――
大学を卒業して、何をして働こうかと思っていたんですが、友だちの紹介で、川崎の柿生というところへ護岸工事の仕事をしに行ったんです。川へ十二貫のブロックをどんどん運んで・・・。
それが終わって、「さて、どうしようかなぁ」と思っていたら、生田の方の仕事が来たんですが、「もういいや」と思ってやめたんです。
大学時代に『カチューシャ』という歌声喫茶でボーイのアルバイトしてたんですが、そこでアコーディオンを弾いている佐藤博さんとパッタリ会ったんです。「お前いま何やってんだよ」「工事をやってたんだけど、やめたよ」「今度おれ、巣鴨で歌声喫茶をやることになってるんだけど、来ないか?」「行く行く」ということになりまして…。
佐藤博に「白十字」なる歌声喫茶を斡旋され、「ボーイでもスタッフでもなく、お前は今日から舞台に出て歌を歌え」を指名された。
三枚目の歌手として聞き覚えのロシア民謡や独唱を歌い、変わり者の歌手としてその日を送っていた。
1963年頃、児玉某という贔屓の客に松竹映画へ紹介してもらい、カメラテストまで合格したが、諸般の事情で取りやめとなった。
それから間もなくして神奈川県川崎市の歌声喫茶「エルサルバドル」に移籍し、「リーダー」なる役を勤めている時、昭和こいると出会った。
そして、歌声喫茶に出入りしていた明石光司に漫才師を勧められ、獅子てんや・瀬戸わんやに入門することとなる。
昭和こいるの前歴
ボケ役の昭和こいるは群馬県伊勢崎の生まれ。実家は伊勢崎の街中に店を構えた「ヨシヤ化粧品」。その次男として生まれる。
経歴は『東京かわら版』(1999年7月号)の聞書きに詳しい――
こいる (小学校の頃は)ひょうきん者でしたね。
目立ちたがり屋というんですかね。学芸会をすると必ず引っぱり出されてね、主役じゃないんだけど、三枚目的なことをやったりしていました。
通信簿にも「とても剽軽で、クラスの人気者」だと書いてあったのを覚えてますよ。「もう少し落ちつきがあれば」とも書いてありましたが(笑)。
のいる おれもそうだったよ(笑)。
こいる だいたいこの世界へ入ろうという人は、 あんまりおとなしいという人は……ね。ま、中にはいるでしょうけど、だいたいがね。
だから、学校時代の友だちは「お前がこの商売になったのは不思議じゃないな」という感じでした。
伊勢崎市立南小学校から南中学校に入りました。春風亭勢朝君がぼくの小学校中学校の後輩ですよ。三遊亭ぐん丈君が、同じ市内の北小・北中なんです。
もう一人、ボクシングで世界チャンピオンになった小林弘は、小中学校の後輩で、高校時代に通っていたボクシングジムでも後輩だったんです。ですから、鈴本で何十周年かの会をやったときも来てくれたんです。
小学校のときに大病をしまして、生きるか死ぬかに近いような状態だったらしいんです。あの頃、自家中毒と言いまして、薬もいい薬もなくて。でも、高い薬を何とか手に入れて、それでどうにか助かったって話なんですけどね。
どちらかと言えば弱い方で、中学まで懸垂ができなかったんですよ。その反動ですかね、学校の勉強はともかくとしてね(笑)、絵を描いたり歌を歌ったりというのは好きだったんです。
小学校一年生の担任の先生が音楽の先生だったんです。音楽の授業が終わってから、ぼくに「太一ちゃん、ちょっと歌やってみようか」と言って、一人だけで教えてもらったりしたこともあるんです。その先生がいたんで、この世界へ入ったということもあったのかも知れないですね。
あの頃、NHKに「子供ののど自慢」というのがありまして、それに「出なさい」と言われて出たんです。鐘が二つと三つと、それから二つ半というのがあったんですが、ぼくは二つ半をもらったんです。
そうやって学芸会でも何でも、歌ったり何かをやったりするのが好きだったんです。
高校は館林にある関東学園というところでした。もともとは短期大学だったところで、私は第二回目の卒業生でした。
高校時代に、街にボクシングジムがあったんです。ぼくは体が弱かったんで、鍛えようとボクシングジムに通ったんです。
ぼくが入ってしばらくしてから入ってきたのが、先ほども言いましたが、後に世界チャンピオンになる小林弘さんなんです。
学校が終わると、毎日ジムへ通いました。二年ちょっとぐらい通いました。それから、懸垂もできるようになって、自分でもびっくりするぐらい体力がつきました。それまでは、年中冬になると風邪を引いたりなんかしてたんですが、風邪も引かなくなって。親も「通って良かったね」と言ってました。
ボクシングジム時代、小林弘はそこまで強くなく、東京の中村プロに引き抜かれてやっと強くなった――というのだからおかしい。
高校卒業後、音楽家を目指して日本大学藝術学部を受験するも不合格。同大学文理学部に入学している。
1年、声楽とバイオリンの修行に勤しんでいた。2年生の時に芸術学部転部試験を受けて合格。この時、転部組で合格したのがブルーコメッツの井上大輔であった。後に井上と再会しているが、「あっちは大スターのブルーコメッツ、こっちは売れない漫才師で辛かった」と伺ったことある。
芸術学部に合格したのもつかの間、大学に行くことはほとんどなくなり、デパートの階段清掃、飯場の雑用、ショップ店員などのバイトに明け暮れた。たまに大学へ行っても講義には顔を出さず、「ミュージカル研究会」で暇をつぶす日々であったという。
そうした中で川崎の歌声喫茶「エル・サルバドル」に入る。そこでのいると知り合った。
ステージの都合上、時間が伸びたり遅れたりするのをいいことに、舞台の上で与太話をしはじめたところ、客からも思わぬ反響を得た。これを機にのいるとコンビを組むこととなった。
花園のいる・こいるの結成
明石光司の斡旋で、獅子てんや・瀬戸わんやを紹介され、1965年には一度入門許諾の話までこぎつけた。てんや・わんやは「歌田ひごと・笑田ひごと」という芸名まで作っていた。
入門直前に「お金がないので2人ともバイトがしたい。新宿の花園饅頭で1年間バイトに出て稼ぎます。その後に弟子にしてほしい」と直訴、てんや・わんやはこれを許し、2人は花園饅頭で1年奉公することとなった。
1966年、1年奉公の末にてんや・わんやの元に戻る。てんや・わんやから以前から候補に挙げられていた芸名「のいる・こいる」(乗り越えるの語呂合わせ)に、「花園饅頭の恩を忘れぬように」という意味を込めて「花園のいる・のいる」としてデビューを果たした。
1966年4月1日、浅草松竹演芸場で初舞台を踏む。出演者は以下の通り。
大宮デン助劇団「強情くらべ」、三遊亭さん生(川柳川柳)、じん弘と劇団笑いの王様「花に浮かれた酔虎伝」、都々逸坊扇歌、ロマンスガールズ、名和美代児、ぼんくらトリオ、スリーアンバランス、ルンバ・タンバ、ミヤオ・ キヨコ、のいる・こいる、竜二・おこま
その時はこいるがギターを持って聞き覚えの民謡や童謡を奏でるスタイルであったという。『東京かわら版』(1999年8月号)の聞書きによると――
のいる ぼくたちが一番最初に稽古したネタは「日ごと夜ごと」というものでした。その当時のこいうものでした。その当様のぼくらの名前が「ひごと・よごと」でしたから、それにもひっかかっていたんです。それを二人で口合わせの練習をしたんです。日常茶飯事にいろんなことがあるという、桜が咲いてどうしたこうしたという、日常のネタでした。これは実際には高座にはかけませんでした。
こいる これはしゃべくりで、歌は入っていなかったんです。ぼくたちの初舞台は、昭和四十一年四月一日、浅草の松竹演芸場だったんですが、 この時は歌のネタでした。ギターが入るネタだったんです。
最初はギターを持たずに、歌の話をずーっとしていて、「じゃ、この辺でまともにやろうじゃないか。そこにギターがあるから持ってこい」とした。
こいる 「かっぽれ」をフラメンコ調で歌う曲でいうので、ぼくがギターを持ってくるんです。
ギターをちゃんとやっていたわけではないんです。趣味でやっていただけで、ブンチャカブンチャカというだけなんです。
のいる ロシア民謡の「カリンカ」とかを歌うんです。
こいる はじめは日本語で歌うんですが、「ロシア語の歌だからロシア語で歌おう。ぼくが解説を入れるから」というので、(のいるが)ロシア語で歌うんです。
のいる あの頃、森繁さんが「フラメンコ・カポーレ」という歌を歌っていて、ちょっと流行っていたんです。
のいる 森繁先生のあの声でね。それをもじって、「カリンカ」を歌っていると、いつの間にかそっちに入ってしまうという……。
こいる そこにぼくが、でたらめな解説を入れるの(笑)。「○△×□×□△×○△・・・」と、わけのわかんないことを言うんです。
のいる 要するに藤村有弘さんがよくやっていたアレですよ。
こいる でも、全部でたらめというわけじゃないんですよ。ぼくはラテンが好きだったから、原語で覚えたラテンの曲があるんです。それをちょこっと入れながら……。
で、のいるさんが「いい加減にしろよ。俺もでたらめだが、お前もでたらめだなぁ」「じゃ、これからもでたらめで行きます」というのが下げだったんです。これが初舞台。
のいる その頃はぼくがボケだったんですよ。
こいる ネタの題名ですか?「春だ桜だ、桜だ歌だ」と言っていたと思います。
ただ、ギターのチューニングが下手だったこと、ギターを持つのが面倒くさいという事情もあり、ギターはすぐに捨てている。
1970年2月、第18回NHK漫才コンクールに初出場。当時、鉄板ネタとしてよくかけていた「マナー教えます」を披露した。当時のパンフレットに――
「マナー教えます」花園のいる・花園こいる
初出場三組のうちのひと組。てんやわんやの弟子である。
のいるは石川県の出身、こいるは群馬県の産。二人とも歌手志望で、歌ごえ喫茶で歌っているころに知り合い、コンビを組んで四年目。
新宿の花園神社の近くの、まんじゅう屋でアルバイトをしていたころの苦労を忘れないようにと、「花園」を亭号にしたというあたり、ひとつの芸界美談。同じアパートに住んでいる。
こいるはさいづち頭を売りものにしているが、のいるにはさして特徴がない。きょうより明日のコンビである。
この時、入賞は逃したものの「いいコンビが出た」と関係者を感心させたという。
かくして漫才コンクールに出たのはよかったものの、行く先々で「花園のい子・こい子」(寄席文字で「る」は少し伸ばして書くため、子に間違えることもある)と女流漫才に間違われる事に嫌気が差し、師匠に「獅子と瀬戸の屋号をいただきたい」と承諾を得た。
新しい名前は「獅子のいる・瀬戸こいる」とまで決まったが、漫才作家の神津友好から「獅子より伸びて、瀬戸を越えるという意味を含めて獅子のびる・瀬戸こえるにしたらどうだ」とアドバイスを受けて、最終的にのびる・こえると変わった。
のびる・こえるに改名
1971年1月1日、「のびる・こえる」と改名。同年2月開催の第19回NHK漫才コンクールにも出場している。パンフレット曰く――
獅子のびる・瀬戸こえる
「昨年は花園のいる・こいるの芸名でいろいろお世話になりましたが、本年より今日この生きと共に、芸名を改めさせて頂きました従来通りご指導、ごべんたつのほどお願い申し上げます。」
というのが、二人がことし出した年賀状の一節である。のいる改め獅子のびる、こいる改め瀬戸こえる。名付親は神津友好君。新しい芸名でもわかるように、てんや・わんやの門下である。てんやわんやは弟子を取らない主義を通しているので、このコンビただひと組の弟子となる。それだけに師匠の彼らに対する期待のほども大きい。
のびるは石川県の出身、さいづち頭のこえるは群馬県の産。二人とも歌手志願で、歌ごえ喫茶で歌っているところを知り合って、コンビを組んで五年目になる。芸風もあまり奇をてらわない正統派。それだけに将来”のびる”可能性のある有望株。師匠の域を”こえるか”どうかは、本人たちの努力にかかる。
去年(のいる・こいる時代)につづいて二回目の出場。新ネタで野心をもやす。
さらに1972年2月の第20回漫才コンクールにもこの名前を出ている。パンフレットに――
獅子のびる(金沢)瀬戸こえる(伊勢崎)
お師匠さんは…
獅子てんや・瀬戸わんやの御両人。
これまでは?……
とにかく二人とも・・・大学にいきました。そしてあげくの果てが川崎市の唄声喫茶でアルバイトにはげんでいたそうです。
「何故かと言うと…僕は(のびる)唄が大好きでしたし、こえる君は、日大でクラシック音楽を勉強してたんです』…このお店に…二人の唄とお喋べりをきいていた…或る歌手が…肝ジンの唄よりも…お喋りの面白い御両人に…「君達漫才やれヨ…その方がピッタンコだよ……」「そうでしょうか」「てんわんさんに話してあげるからサ…弟子入りしてみたら…」
運命は…そして現在6年目…今日の御両人をここに誕生させたことになるのです。
これからは?…
あくまでも師匠てんやわんやの線をねらって、二代目てんやわんやになるつもり…とか。
「二人で酒を相手に…「あ、でもない」「こうでもない」と…ネタのねりあいをするンです、徹夜で…話しあうんです。師匠達は年のせいかこれは出来ませんからネ、それを思うと、それだけ僕達の将来は明るいと思います」と、燃えてました。
しかし、のいるが急性肝炎になってしまった上に仕事もキャンセルになるなど、縁起の悪いことが立て続けに起こったせいもあり、「この名前もよくない」となった。
1972年頃、師匠の付き人として日劇の三橋美智也ショーに参加をしていた(同年5月のリサイタルか)。三橋美智也はてんや・わんやを通じて「昭和の時代を超えられるような芸人というので、昭和のいる・こいるはどうか」と提案。めでたくこれが採用となり、生涯名乗り続ける芸名となった。
昭和のいる・こいるとなる
1974年2月、病を克服した二人は「昭和のいる・こいる」として第21回漫才コンクールに出場し、「くたばれベースボール」を披露。当時のパンフレットに――
④……漫才は、底抜けの明るサが、ドボーンドボーンと寄せては返す波のように舞台にただよってなければ、本当はいけませんネ「俺、先月のアパート代、まだ払えないンだぜ」とは言うものの”なんのその‼”
衣装というユニホームをバッチリ着込み、「顔に合わないニューモード」「財産に合わない仕立代」もなんのその‼”
昭和のいる・こいるさんを見て下さい。明るさが年をとらせないコンビとなっているじゃありませんか、お客様に「好きだなアー」と言わせますヨ…そこが。
この年、優勝が期待されたというが入賞にも至らずがっかりしたという。
若い頃は獅子てんや・瀬戸わんやそっくりの漫才で「堅実であるが個性がない」という批評が付きまとった。
若い頃の「マナー教えます」「くたばれベースボール」などでは、「野球が好きだ」というのに対し、「ひいきのチームが勝って何になる、金にもならないことをして」と罵倒する――というような毒舌漫才の路線も目論んだがうまくいかなかった。
1975年3月、第23回漫才コンクールに出場し、『テレフォン物語』を披露したが、この時は元気がなく、優勝を逃した。遠藤佳三『東京漫才うらばな史』でも――
のいる・こいるは前回長蛇を逸してから自信をなくしたようで、しばらく元気がなかった。コンクールへの意欲もいまいちだった。この回演じた『テレフォン物語』は、師匠の獅子てんやさんからヒントをもらって作ったネタだった。電話番号の記憶法など電話についてのウンチクを並べた内容だった。彼らなりに真剣に取り組んだネタだったが、テーマがいかにも小さかった。優勝候補にふさわしいものでなかった。とはいえ、当日の出来は立派なもので、笑いも十二分に取れていた。それが再びまったくの選外になったについては、審査員の微妙な配慮があったと思う。
と記されている。
そうした中で、二人は「民謡漫才」に活路を見出した。遠藤佳三『東京漫才うらばな史』に――
のいる・こいる「民謡あれこれ」(自作)は、民謡上手を自称するこいるが、いざ歌いはじめるとえらく調子っ外れで、のいるにさんざん攻撃されるという筋で、それまでの彼らにない賑やか一式のネタだった。彼らは新宿の歌声喫茶「灯」のステージで歌唱指導をしていたことがあり、歌に自信を持っていたが、漫才に転じてからは、しゃべくり一筋を心がけて、歌は封印していた。
『民謡あれこれ』で初めて封印をといたのである。三橋美智也ショーに加わって地方をまわりながら、ネタ固めをしたという。当時、新山ひでや・えつやが民謡ネタで売り出していて、のいる・こいるの民謡ネタはひでや・えつやのあと追いの感もあったが、『民謡あれこれ』は、民謡をヘタに歌って笑わせる点で、のいる・こいる独自の手法だった。
ネタはどこから見ても完成品だったが、彼らはまだ不安だったようで、ある時、私に補作を頼みにきた。「作家のセンスで存分に書き直してもらえませんか。そして遠藤佳三作と呼ばせてもらえませんか」というものだった。私は、
「補作は引き受けるが、作者がきみ達だということはみんな知ってるので、私の名で通るわけがない」
と返事した。だが二人は前回、前々回と続けて入賞にかかわった私の名を借りて縁起をかつぎたい気持ちがあるようだった。そうなると私も断りきれなかった。
こいるが原稿用紙に達者な文字で書いてきた台本(題は「民謡教室」だった)は、やはり完成品だった。私は冒頭のやりとりの一部をあえて変更し、中盤に、
のいる「おまえさんの歌はこま切れだ」
こいる「あちこちから「素敵ぃー」って声がかかるんだぞ」
のいる「なに言ってんだ。こま切れがステーキになるか」
など、くすぐりを三つ四つ加えた程度で、私の字で清書をして、彼らにもどした。ただし、表紙には麗々しく遠藤佳三作と記し、稿料もオリジナル一本分に当るものを受けとった。
と裏話が出ている。遠藤氏にその辺りのことを少し伺ったことがあるが、「本気で優勝する気だったんでしょうねえ」と言っていたのを思い出す。
1976年3月、第22回漫才コンクールに出場し、「民謡あれこれ」を披露して、優勝。出場者は――
10 同棲時代 青空ピック・アップ
6 新婚旅行 東京丸・京平
8 カントリ・ソング 大空あきら・たかし
7 ブルースリーの伝説 大空せんり・まんり
1 浪曲七変化 さがみ三太・みなみ良太
2 民謡あれこれ 昭和のいる・こいる
5 ぼくのアパート 高峰愛天・東天
4 それは先生 高峰和才・洋才
9 ぼくはスポーツマン ツービート
3 君よ変革を志せ 星セント・ルイス
と、後の漫才ブームの担い手ばかりが出場している。
優勝後、ブレイクする――と思いきや、演芸ブームの終焉もあり、パッとせずに続いた。
さらに漫才ブームの時代になっても、選ばれる事なく、むしろ優勝しそびれたさがみ良太・三太、ツービート、漫才ブーム直前に優勝した星セント・ルイスがよく売れたこともあり、辛酸をなめた。
若き日のビートたけしから「漫才コンクールに優勝しても何もならない。昭和のいる・こいるなどがいい例だ」といじられるほどであった。
三橋美智也などの司会漫才として全国を回る中で、ある時、のいるの話をこいるが聞かない。こいるは面倒くさそうに「ふんふん、ああそう、はーはーはー!」というのいるの話を聞き流す態度が大うけを取った。
この意外な芸風に活路を見出した二人は、これを機に「これを漫才に取り入れたらいいのでは」と考え、本格的にその路線を他同様になった。
如何にも真面目そうなのいるに対し、こいるが「はー!はー!」といい加減に受け流す漫才を展開。東京漫才のホープとして注目を集めるようになった。
1984年11月10日、漫才協会の真打として認められ、浅草公会堂の漫才大会において9代目真打昇進。
昭和のいるこいる真打披露御挨拶
獅子てんや・瀬戸わんや
本日は漫才大会に賑々しく御来場頂きまして有難とうございます。
さて此の栄えある漫才大会の席にて、昭和のいる・昭和こいる両名が漫才協団の諸先輩の御推薦を頂き、又御贔屓すじの御支援もございまして、真打昇進を披露させて頂く事になりました。此処に深く感謝と共に御礼申し上げます。
昭和のいる・昭和こいる両名はコンビを結成致しまして今年で十八年、皆々様の御支援、御協力を得まして今日まで精進して参りました。而し最近皆様御存知のように、演芸界も不調でございまして、近年には東宝演芸場、松竹演芸場等の伝統ある寄席演芸の火が消えてしまいました。又テレビ、ラジオ等も演芸番組が少く、演芸を御披露する場が全く無い現状でございます。その中で漫才を志して行く事は誠に至難な道でございますが、何んとか再び演芸界が花盛りになります事を念じまして、両名がますく「芸」に精進致す決心でおりますので、何卒皆々様には今後共、より一層の御支援と御援助を切にお願い申し上げます。
本日は御協力を頂戴致しまして、心から厚く御礼申し上げ、御挨拶させて頂きます。
てんや・わんやの指摘通り、「寄席演芸の火が消えた」という中での昇進であった。そうした中で東京漫才の本流と共に歩んだのは大きな功績だろう。
昇進披露には、師匠のてんや・わんや、コロムビアトップ、リーガル天才、青空一夜が並び、ゲストに三橋美智也、二葉百合子などのキング所属の歌手が出演した。
この頃より落語家の引きで落語協会の寄席へ度々出演するようになった。鈴々舎馬風の内輪となり、落語会のゲストなどにも出演するようになった。
1985年には、なじみのキングレコードより歌謡曲『一気酒・のろけ節』を発売。しかし、この直後にこいるは胃潰瘍に倒れ、胃の3分の2を摘出している。
1988年7月、正式に落語協会会員となり、色物として出勤を続けた。
二人の品のいいしゃべくり漫才は、寄席の世界と二人の明朗な話術は馬が合った。
当人たちは「ネタが三つしかなかった」と自嘲しているが、寄席の客層に合わせてアドリブで話を変えられる自由さと達者さは評価を受けた。『東京かわら版』(1999年11月号)の中でも――
のいる ぼくら、落語協会へ入れていただいて十二年ですが、ネタ三本しかないんですよ(笑)。
こいる うん(笑)。
だから、ぼくらの場合、同じネタでも(細かいところは)全部違ってますよ。言い回しなんかはその都度変わりますから。
――それはぼくは、演芸の一つの理想的な形というか境地なのではないかと思うんです。
こいる「今日のお客さんには歌は無理かな……」 と思ったら、パッと別な話に持っていったりね。
のいる 話はころころ変わりますからね。
平成初頭には「実力派漫才師がいる」と寄席の中で話題を集めるようになった。
遅れて来たブレイク
そんなのいる・こいるの実力を買う芸人や歌手も多かった。
歌手の玉置浩二も大ファンであり、後に『そんなもんだよしょうがない』の作曲を提供している。二人の売り出しに尽力した高田文夫氏が語った所によると――
「玉置さんが一時期、軽井沢に引っ込んでいた時、落ち込んだり元気がなくなると、この二人の漫才が聞きたくなる。寄席に『のいる・こいるは出ますか』と出番を問い合せて、二人の漫才をききに東京まではるばる寄席を訪ねるほどのファンだった」
高田文夫の推薦で、1999年1月1日、フジテレビ系列『初詣!爆笑ヒットパレード』に出演。この出演で大爆笑を獲得した二人は、大ブレイクをとげる。
同年2月21日には「初登場!昭和のいる・こいる」という大鳴り物入りで『笑点』に出演したほどであった。
以来、忙しく働く日々が続き、2000年3月17日には浅草芸能大賞奨励賞を受賞。
同年12月には高田文夫作詞・玉置浩二作曲の歌謡曲『そんなもんだよ、しょうがない』を発表。高田文夫発行の『笑芸人4 満開!東京漫才』でも大きく取り上げられるほどであった。
それ以降は東京漫才の大幹部となり、漫才協会の幹部に就任。さらに正月番組や寄席番組ではおなじみの顔になった。『笑点』や『笑いが一番』など演芸番組が少なくなる中で、年に何度も出ていたのはその人気と実力ありきといえよう。
70過ぎてもカクシャクと活躍し、新ネタなどにも挑戦していた。2000年代から2013年までの10年ほどの活躍はすさまじく、毎月のように『お好み寄席』『真打ち競演』『笑いが一番』に出ていた。
後年は話術も安定し、こいるが「ヘーヘーホーホ」と相槌を打つと客の中にも口ずさむ者もいたほどであった。相槌が始まると客の爆笑もおこったほどである。
長らく東京漫才の大スターとして第一線で活躍を続けていたが、2013年頃より相方の体調不良によりコンビ活動停止が余儀なくされる。
2013年7月23日の浅草演芸ホールを最後にコンビ活動を停止。のいるは療養生活に入った。
当時、相方を失っていたあした順子とコンビを組み「順子・こいる」として再スタートを切った。2013年11月の漫才大会でお披露目していおる。
歌ネタが主体で、こいるが自慢の喉を聞かせようと奮闘するが順子に邪魔をされたり、頭にハンカチを乗せられたり、操り人形のように動かされて「ハイハイハイ」と変な風になってしまう――古き良き漫才を演じていた。
2017年頃、あした順子とコンビを解消(解消は明言しなかったと思うが)、独立して漫談に転身。東洋館などを軸にしゃべくり漫談を演じていた。
この頃よりガンが悪化し、闘病しながら高座に出ていた。
2021年11月28日、有楽町よみうりホールの「来年三月真打決定 鈴々舎八ゑ馬の会ファイナル」にゲストとして出演。鈴々舎馬風や笑福亭鶴瓶などに挟まれて漫談を披露。
その頃すでに体調は相当悪化しており、高座から降りるや「最後の力を振り絞った。これが最後の漫才だろう」とこぼすほどであった。
それから間もなく入院。最後の舞台から1月後の12月30日午後、前立腺がんのため東京都北区の病院で息を引き取った。
一方ののいるは車椅子に乗るようになり、実質引退状態となっていた。2017年2月のチャンス青木の葬儀に出席した際は確か車椅子であったはずである。
導師役をつとめていた甘味けんじ(僧侶でもある)に向かって「甘味!持ち時間守れよ!」といって大爆笑を買っていた――と漫才協会の面々からうかがったが、どうだったか。
相方が亡くなった後も漫才協会と落語協会にも籍を置いていた。青空たのし亡き後は漫才協会の最高齢の長老となっていた(次は1937年2月生まれの真木淳)。
長らく老後生活を送っていたが、2025年5月24日午後7時45分、肺炎のため東京都内の病院で死去。88歳であった。