玉子家源一

玉子家源一

源一・一丸(右)
人 物
玉子家 源一
・本 名 井原 嘉平
・生没年 1897年6月11日~1986年10月15日
・出身地 福岡県宗像市(旧・津屋崎町)
来 歴
※玉子家源一氏のご遺族のご協力をいただきまして、無事に頁を完成させました。
ご協力、厚く御礼申し上げます。(ご遺族様のサイト 玉子家電脳社)
関西で修業をした後、志ありて上京し、そのまま東京に根を下ろしたタイプの漫才師である。こういうタイプは戦前、特に東京漫才が出来る前後――即ち、震災前後に多く、林家染団治などもこれに該当する。東西の漫才の関係や流れを知る上では欠かせない存在というべきであろう。
漫才師以前
玉子家源一は福岡県津屋崎町、現在の宗像市の生まれ。実家は小間物屋――現在のスーパーマーケットのようなことをしていたそうで、なかなか裕福な家柄だった。幼い頃は海の近くで育ったらしく、晩年まで故郷の風景や思い出を度々回顧していたという。
故郷では「カド屋のカァちゃん」(カド屋が屋号なのか、渾名なのかは分からなかったが)という愛称で慕われたらしく、店の手伝いや行商などを行っていたそうである。
しかし、芸事や遊びにハマってしまったのが運の尽き、実家の潤沢な資産を盾に、色事や遊びごとに熱中し、都々逸、小唄端唄、三味線、音曲など、芝居に出てくる若旦那のような放蕩三昧な生活を送るようになってしまった。
ご遺族によると、「小原庄助さん状態」(民謡「会津磐梯山」に出てくる伝説上の遊び人)だったというのだから、相当な放蕩ぶりだったようで、それが元で身上を潰し、芸人になる遠因になったともいう。後年、親族などからは「あれだけ遊んでいれば……」などと皮肉を言われたというのだから、その遊びっぷりが如何なるものであったかは、想像することが出来ない。
一方、親の勧めか、本人の希望かわからないが、当時としては高学歴の旧制福岡商業学校に進学。ここで商売の基礎や経理、計算などを学んだらしく――これは後年の役に立つのだからよくわからないものである。
漫才師になるまでの経緯は『都新聞』(1935年8月22日〜3日号)掲載の『漫才銘々傅』に詳しく掲載されているので引用する。
初め福岡商業學校に學んだが、中途退學して、それから満洲に遊んだというが、半年ばかりすると現実的な事を考えるようになり、暫く遊んで、不動貯金銀行福岡支店に入り集金係となつた
銀行勤めの傍らで芸人たちと遊び、時には素人演芸会などを催すようになったそうで、仕事もなおざりになってしまった。当然、その行状は会社の間で問題になり、批判の的に。また、堅実な社風と相容れられないと感じた源一は銀行を退職。『漫才銘々傅』には「集金係井原嘉平、依頼解雇、大正十四年二月廿三日、株式會社不動貯金銀行福岡支店」とある。
なお、この退職は身の上の事情での決断で、決してやましい事があっての退職ではなかったという。
上京と東京漫才
退職後、一旗揚げようと大阪へ出向くが、うまくいかず、逍遥する日々を過ごした。
そこへ銀行員時代に目をかけていた芸人から「旦那は藝はあるんだから、當座凌ぎに一つ色物の席にでも出て見ませんか、私がお世話しませう」と、千日前にあった子寶席という色物専門の寄席を紹介してもらい、そこに出演。
「最初はいろんな藝を披露してゐたが、その内勧められて漫才をやり出したらこれが受けた、その頃源一の舞臺を見た玉子家源丸が大いに感心し、いろ/\注意、助言してくれた事が縁となつて、その門下に加はる事になり、この時から玉子家源一の名が生れた」
という。なお、源丸は玉子家圓辰の高弟で、当時、上方漫才の大御所であった。
その後、師匠について漫才を磨き、独立。1926、7年頃には早くも東京に進出していており、『都新聞』(1927年5月3日号)の広告に、
「▲音羽演芸館 万歳玉子家源一加入」
とあり、『漫才銘々傅』には、
「かうして大阪で藝を叩きあげて京都、名古屋等と旅廻りをし、あこがれの東京へ出て今のオペラ館、當時の浅草劇場の舞臺を踏んだのは翌年初夏の頃であつた」
とある所から、1926年頃には上京していたことがわかる。
当初は相方を変えては組みなおす日々を過ごしていたそうで、
「淺草劇場で最初の相手役は浅田家日佐丸といつたが、こゝを半月程で御園劇場、今の玉木座に移つた時は河内家玉春と變つたなど源一の舞臺での女房役は随分と變つた」
とある。この日佐丸は後年、「浅田家」なる一派を起し、上方漫才の大御所となった。
その後は、玉子家源六、砂川君代、出雲友衛、荒川芳夫、若松家正三郎などを経て、1931年頃、兄の玉子家一丸とのコンビに落ち着いた。『都新聞』(1931年11月13日号)に
▲萬歳舌戦會 十三、四両夜牛込亭に、出演者は、吉丸、明月、花香、万龍、金茶九、一丸、芳子、小ゑん、松江、正三郎、九州夫、静子、一丸、源一
とあるのが最初の記事か。いずれのコンビも俗謡の「ドンドン節」を取り入れた漫才を得意にし、「ドンドン節の源一」として、浅草を中心に売れた。
一丸とのコンビで静家演芸社に入社、華々しく売り出され、東京漫才の売れっ子の一組として数えられた。
1937年7月9日には、ラジオに初出演し、話題を振りまいた。以下は『読売新聞』(同日)の引用。
漫才『唄の旅行』 浅草の靜家演藝社専属の玉子家一丸(三七)源一(三五)兄弟は一昨年秋浅草公園劇場で催した関東関西漫才大會一等入選者、福岡の出身で源一は福岡の不動貯金銀行の行員だつたが震災後漫才に転向し一丸は小學校の先生だつたが八年前弟の後を追つて漫才家さんとなつた兄弟ともけふが初放送
長らく浅草の劇場を中心に、人気を集めていたが、1938年、兄・一丸とのコンビ解散。
この時期、人気コンビが続々と解散した事もあって、『都新聞』(10月6日号)に『呑気な商賣に悩み在り 漫才に夫婦別れ續出 笑の世界に笑へぬ悲劇』に取り上げられた。以下はその引用。
そのお次は玉子家源一と同じく一丸のコンビで、これも前二組に劣らない程長年に亘る、而も仲のいいコンビで知られたのをアツサリ別れて先づ弟ながら舞臺で兄貴だつた源一が、玉子家音之助といふ相手を得て、気分一新ではじめ出した
とある。一丸は引退して、サラリーマンとして、松竹に入ったとご遺族の噂であるが――
兄・一丸とのコンビ解散後は中村音之助、戦時中には東駒千代ともコンビを組んだ。
また、源一にはキャリアがあり、漫才師の中でも知識があった事から、帝都漫才協会の役員に任命されている。昭和18年における役職は『理事会計』。昔、商売をやっていたという経験が多かれ少なかれ、この役職につながっているのではないだろうか。
戦時中は慰問や官僚たちのお座敷で活躍したといい、ご遺族によると、『東条さんとか海軍大将さんなんかの近くにせいか、生活には困らなかったし、まさか日本が負けるとは思ってもいなかった、と後年語っておりましたよ。』との事。
話を聞く限り、どうやら、源一は、時々昔を思い返しては、「愛宕山時代の放送に出た」、「大臣さんの近くにいた」「慰問にも回った」などと、懐かしそうに語っていたという。(目下調査中)
しかし、戦争末期はそうもいかなかったようで、東京大空襲をはじめとした空襲などで焼き出されてしまった。
戦時中及び敗戦直後までは、埼玉県桶川市に疎開していたらしく、『芸能タイムス』(第8号)の「演劇笑話」(井口政治)の一節に、
漫才連中も据勝(註・砂川捨勝か)が葛飾郡鎌倉町に源一が埼玉県桶川町に
とある。詳細は下記画像を参照のほど。ここに記された漫才師は、砂川捨勝、玉子家源一、荒川小芳(内海好江の父親)、松島家圓太郎、林家染團治である。
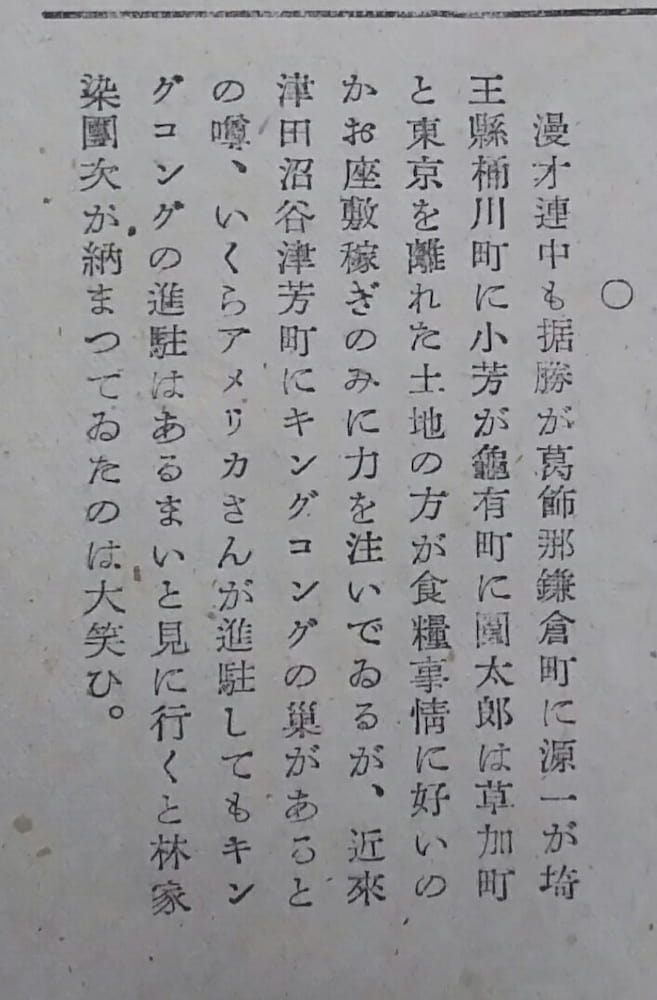
セミリタイアと晩年
終戦後、昭和20年前半まで一応舞台に立っていたようである(ご子息は昭和23年ごろ、松竹演芸場でご覧になられたという)が、相方と別れ、コンビを組む相手がいなくなったのを機に、漫才から足を洗い、「玉子家芸能社」の社長として再出発をした。
当初は浅草に事務所を構え、仕事を行っていたそうで、設立前後から、一応知名度はあったようである。ご子息曰く、「住所をいちいち書かなくても、『台東区浅草 玉子家』って書いて送ればちゃんと届いたって、自慢していましたよ」。
昭和27年、江戸川区に引っ越し、新たな「玉子家芸能社」を設立した。この頃はまだ戦前の人気の名残があったようで、近所の人から慕われていたという。
芸能事務所の社長としても、相応の腕はあったそうで、昭和30年に完成した、レジャー施設「船橋ヘルスセンター」の入れ方(凱旋)も依頼されていたという。当時、「船橋ヘルスセンター」と言えば、大変な人気スポットで、栄華を極めていた。その施設内には芸人の出演するステージや劇場もあったという。
1969年10月、一線を退いていた源一であったが、青空うれしやリーガル天才らの後押しで、大朝家五二郎、林家染団治と共に『東京漫才の長老』として、「東宝名人会」に出演し、昔話に花を咲かせた。演芸評論家の三田純一は、この舞台を見て、
大朝家五二郎、玉子家源一、林家染団治――若い寄席ファンにはなじみのない名前だが、いずれも漫才界の長老である。「東宝名人会」の土曜の昼席、めずらしくこの三人の顔がならんだ。「なつかしの演芸」というタイトルだが、司会の青空うれし・たのしのインタビューが主で、かんじんの“演芸”が見られなかったのが残念。わずかに、染団治が十八番の“ゴリラの安来節”をやって、オールドファンをなつかしがらせた。この三人、いずれも大阪で修業し、震災後東京に定住したという経歴であるのも、漫才は西から、という芸能史の一コマをうかがわせて興味があった。
(「朝日新聞・夕刊」 昭和44年10月21日 9頁)
と、なかなか興味深いコメントを寄せている。この時にはもう、コンビを組んで漫才をやっていたのは染団治だけで、五二郎も源一も芸能社をやっていたというのは何かの因縁であろうか。
推測ではあるが、これが芸人・玉子家源一としての最後の大舞台であり、公の立派な劇場に出た最後の記録ではないだろうか。その後、新聞や雑誌を探っても、源一の名前は殆ど出てこなくなる。
ご遺族のお話によると、晩年は芸人の凱旋や事務所の仕事をつづけながら、老人会などの余興で、若い頃覚えた芸を時折演じていたという。昔取った杵柄とはこの事であろう。老人会などの間では、結構な人気者だったようである。
また、青空うれし氏によると、「漫才師としては珍しく、品のいい人で、如何にも育ちのいい感じの社長な感じだった。ゴロツキ興行主の多かった時代にしては、物腰の柔らかい人だとは思ったな」とのこと。
最期は、数え年90歳という天寿を全うし、この世を去った。葬儀の折には、十八番であった「ドンドン節」のテープを流し、故人を偲んだ、という。何とも粋な芸人冥利に尽きる話ではないだろうか。
先日、息子さんもお亡くなりになられた。生前はあれこれとご教示いただいた。ご冥福をお祈りいたす次第である――
芸 風
俗謡の「ドンドン節」の替え歌を看板ネタとして活躍し、人呼んで「ドンドン節の源一」として大いに売れた。波多野栄一も、「寄席といろもの」の中で、
玉子家源一 音之助 ドンドン節でよく売れた。音之助のあとは「一丸」と演っていた
と、その頃の人気ぶりを賞賛している。しかし、音之助と一丸の順は逆ではないだろうか。
そもそもドンドン節とは、『明治末期から大正初期のはやり唄。浪曲師の三河屋円車が唄い、楽屋で太鼓をどんどんと打たせて人気を博したのが始まり。「駕籠で行くのはお軽じゃないか」で始まるものが有名。』(大辞林)というようなもので、浪曲師のうなりをヒントに、演歌師などが改良して広めた曲であった。当時、浪花節の一節を改良して、一曲に仕立て上げるといった事は頻繁に行われており、「奈良丸くづし」などはその類である。
このドンドン節が生まれる経緯には、三河屋と桃中軒雲右衛門との確執があったというのを、バイオリン演歌研究家の人から聞いた事がある。曰く、
このドンドン節のヒントになった円車の師匠は梅車といって、中部近辺で大変売れた浪曲師だった。この人の家内が、お浜さんと言って、大変達者な曲師であったが、梅車は人間が難しく、事あるたびに家内に強く当たるので険悪な関係になっていた。
そんなお浜さんといつの間にか仲良くなってしまったのが、当時、吉川繁吉と名のり、梅車の一座で修業していた雲右衛門であった。二人は相思相愛になり、遂には梅車の下から駆け落ちをしてしまう。
これだけならばよかったが、繁吉はお浜と手を取りあってあれよあれよという間に成功してしまい、遂には日本一の浪花節語りになってしまった。
梅車の悲憤慷慨は幾許なるものだったか、弟子の円車はまるでその意趣返しの如く、寄席に出ては、太鼓を入れさせた節回しを生み出し、これを演歌師の後藤紫雲が取り入れて、流行させた。
という。しかし、その一方で、当時浪曲師は一席終わると余興として、都々逸や民謡、節真似等を興ずることがあったので、ドンドン節もその延長線上にあったのではないか、という解釈も出来ない事はない。
話がずれてしまったが、当時よく歌われていたドンドン節の見本を挙げて、筆を置く事にしよう。
駕籠で行くのは お軽じゃないか 私しゃ 売られて行くわいな 父さんご無事で また母さんも 勘平さんも 折々は 便りを聞いたり聞かせたり ドンドン
(忠臣蔵より。これが本歌のような物)
伊勢は津でもつ 津は伊勢でもつ 尾張名古屋は城でもつ うちの所帯は あのかかあでもつ かかあのゆまきはヒモでもつ ヒモの虱は皴でもつ ドンドン
(伊勢音頭の文句から)
駕籠は行くのは 海老ではないか 私しゃ 売られてゆきますよ 向こうの蕎麦屋と こちらの料理屋へ 1キロいくらで 買い取られ 皮をまた剥かれたり 首をちぎられて 白い衣をつけられて 油の中に ちょいと入れられて 熱い思いはするけれど おまんまの肌に乗る テンドン
(ご遺族様のご指摘なさる「テンドン節」はこういった歌詞に近かったのではないだろうか)


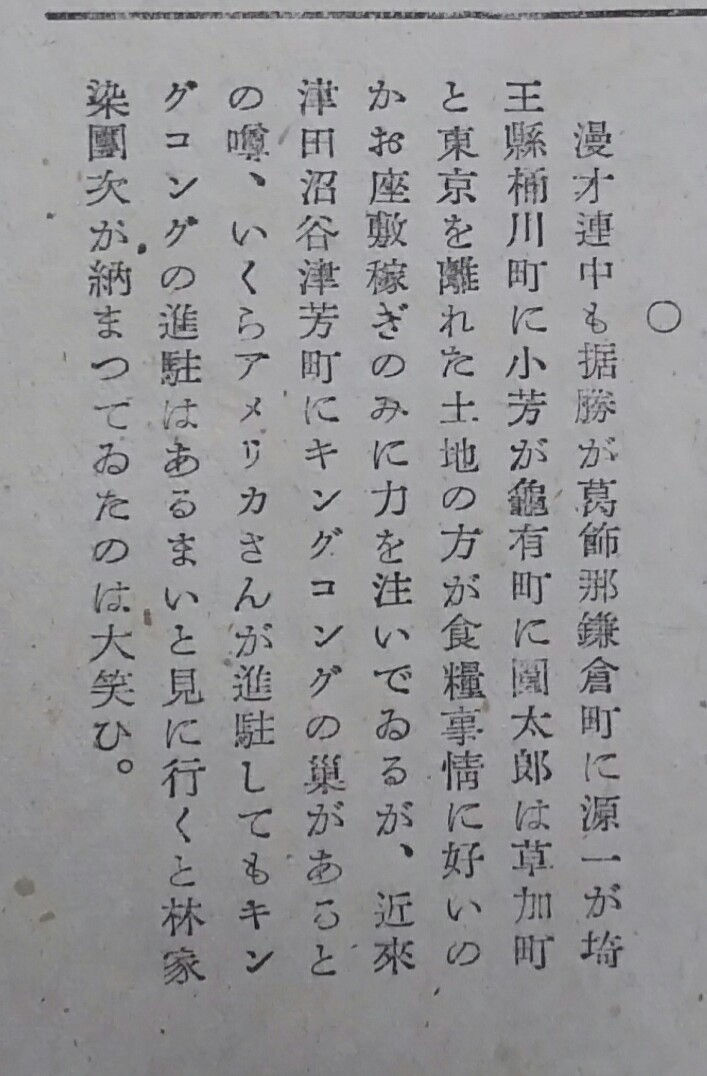

コメント